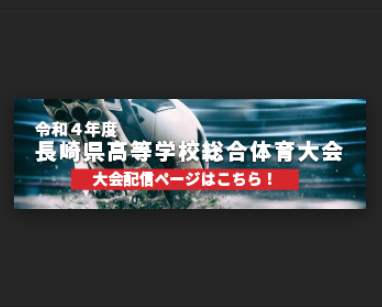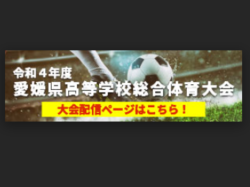credit: Mark Baylor via FindCC
credit: Mark Baylor via FindCC
2015年度より小学生サッカーの主要な大会の日程やその開催方法が大幅に変更になります。
たとえば全日が夏ではなく冬の開催になったり、ナショトレも各地域にとどまらず全国規模で開催されることが決定しています。
このページでは2015年度のU-12の主要な大会の予定を中心にまとめてみましたので今後の予定を立てる際の参考にしてみてください。
なお、あくまで予定のため変更になる可能性もありますのでご注意ください。正しいスケジュールはサッカー協会HPよりご確認ください。
2015年度 U-12主要な大会年間スケジュール
■4?12月 【こくみん共済U-12サッカーリーグ】(全日の予選を兼ねる)
■5月3日?5日 【JA 全農杯チビリンピック 小学生選抜 8 人制サッカー大会】(神奈川/日産スタジアム)
■7月29日?8月2日 【JFAフットボールフューチャープログラム/トレセン研修会U-12】(静岡/時之栖)
■8月14?16日 【バーモントカップ第25回全日本少年フットサル大会】(東京/駒沢体育館、大田区総合体育館)
■11月 【全日本少年サッカー大会都道府県予選】
■12月26?29日 【第39回全日本少年サッカー大会】(鹿児島/鴨池陸上競技場他)
[amazonjs asin=”4098401088″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”サッカーで子どもをぐんぐん伸ばす11の魔法 (edu book)”]
全日本少年サッカー大会が6年生の集大成に
 credit: MSC Academy U12 Green via FindCC
credit: MSC Academy U12 Green via FindCC
今までは8月に開催されていた全日の全国大会。
12月末になったことで、全日がU-12世代にとっては小学生の最後の大きな公式戦となる子がほとんどになります。
また、年間を通して行われる「こくみん共済U-12サッカーリーグ」に参加していることが全日の参加資格となり、さらにリーグの結果を各都道府県大会でのシード権に反映させることが決定しています。
このリーグ戦で一つ一つの試合を大切にし順調に勝ちを増やしていったチームが全日でも有利になってくるため、より一層油断が禁物となりますね。
バーモントカップ・全国トレセンが夏に開催
例年冬に開催されていたバーモントカップが8月の開催に変更になりました。
今まで夏は全日のイメージだったと思いますが、開催日程がバーモントと逆転したような形となりました。
また、全日が冬になったことで夏のジュニアの予定が大幅に空いたということも受け、JFAフットボールフューチャープログラム/トレセン研修会U-12というものが夏に開催されることとなりました。
これは47都道府県から選ばれたトレセンチーム、計48チーム(東京2チーム)が参加し、計768名の選手が集まるため今までにない大きな規模のトレセンとなります。
今までは全国の選手を一斉に集める形でのトレセンU-12を廃止し、9つに分けた地域ごとで開催していましたが、特に地方の選手にとっては刺激が弱くなるなどマイナス面も指摘されていたということも再度開催が決定した大きな要因と言えます。
U-12世代にとってのスキルアップの場だったり目標が一つ増えた形となります。
[amazonjs asin=”4278049145″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”10代スポーツ選手の栄養と食事―勝てるカラダをつくる!”]
この改革で子どもが受ける影響がこんなに
 credit: Mark Baylor via FindCC
credit: Mark Baylor via FindCC
ジュニア世代で本格化するリーグ戦がもたらすものとは?
すでに多くの地域でリーグ戦は導入されていますが、2015年度からは全日への参加条件としてリーグに参加していることが必須となり、さらにリーグの結果を各都道府県で行われる代表決定戦に反映させることが決まりました。
これによって巻き起こるメリット・デメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
様々な意見が飛び交っていますが、その中の一部の意見を参考として紹介します。
メリット?・リーグ戦の導入によって公式戦の強度の高い試合数が増える
 credit: woodleywonderworks via FindCC
credit: woodleywonderworks via FindCC
東京都立川市Tachikawa elf FCの中村太一監督は、
「子どもたちは試合で一番成長をすると感じてきましたので、練習試合にはない真剣勝負の環境が飛躍的に増えたことは大きいですね」
と試合数の増加を歓迎する。
これまで公式戦の主流であったトーナメント方式では、決勝まで勝ち進むチームと、1回戦で敗退するチームとでは経験できるゲーム数に差がでてくる。
選手の育成を観点に考えると、試合経験が少ないことは上達する機会を失っていることにつながるため、すべての選手が平等に出場できる機会を提供しやすいリーグ戦形式の大会は重要になるだろう。
[amazonjs asin=”B0036I1DE0″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”adidas(アディダス) ボール用ディパック ADP18NB”]
メリット?・やり直しのできるリーグ戦で失敗を恐れないようになる
 credit: MSC Academy U12 Green via FindCC
credit: MSC Academy U12 Green via FindCC
2014年の第38回大会で、チームの設立からわずか4年で全国ベスト8まで上り詰めたJFC FUTURO(神奈川県横浜市) の鈴木友監督は、
「選手は、一発勝負のトーナメントだと、チームの勝敗を考えてプレーのリスクを避けることがあります。失敗を恐れて積極的に挑戦することをしなくなります。
ところがリーグ戦では、次にも試合があるのでやり直すことができます。
たとえミスをして1ゲーム目を落としてしまったとしても、その選手に対して、次にチャレンジをする改善の機会を与えることができるのです。これが一番大きいでしょうね」
と、リーグの導入は、選手たちに今までよりもいい環境をもたらすという。
デメリット?・勝ち星にこだわるとリーグ戦のメリットが消えてしまう
 credit: MSC Academy U12 Green via FindCC
credit: MSC Academy U12 Green via FindCC
参加チームが多い地域では、年間のリーグ戦が4月から10月まで組まれてしまうと、全日本少年サッカー大会の開幕までのわずかな期間に、改めて全チームを対象としたトーナメントで代表チームを決める余裕がなくなるだけに、リーグ戦での順位を反映せざるを得ない。
そうなると、リーグ戦の結果次第では予選に参加できなくなるため、リーグ戦で、強い相手には得失点差の開かないように、また同等か格下の相手に対しては取りこぼしのないように固定メンバーで戦い、出場枠の確保に奔走するチームがでてくるのではないかという意見がある。
本来の狙いは、たくさんの選手に経験を積ませる機会を提供するはずなのに、現実はかえって出場人数が少なくなってしまうケースも考えられ、リーグ戦の良さが消されてしまうと指摘する声があがっている。
[amazonjs asin=”4862552536″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”少年サッカーは9割親で決まる”]
勝ち上がることができるのは・・・『リーグ戦の良さ』を最大限取り入れているチーム
 credit: Fernando Herrera via FindCC
credit: Fernando Herrera via FindCC
JFC FUTUROの鈴木友監督は『星取り勘定』のために出場メンバーを固定しても、リーグ戦を勝ち上がることは容易ではないという。
「むしろトーナメントであれば、そのときの状況によってはフロック(まぐれ)で勝ち上がることもあります。極端な話、実力差のある相手との対戦でも、例えば雨でグラウンドがぬかるんでいて、両チームの選手が思ったようなプレーができず、PK戦での決着になって勝ってしまうこともあります。
でも長期のリーグだとそうはいきません。学校の行事や体調によっては毎回ベストメンバーが揃わないこともあるでしょう。
そういうときにチームの総合力が問われてきますから、レギュラー、バックアップメンバー問わず、チーム全員がきちんと試合に出場して『M-T-M(マッチ-トレーニング-マッチ)』に取り組むことができているのが大切になるのでしょうね」
この年代で優先すべきは、一人ひとりが試合に出場する機会を増やすこと
 credit: Michelle Milla via FindCC
credit: Michelle Milla via FindCC
セレクションのない地域ぐるみのサッカーチームである飛田給フットボールクラブ(東京都調布市)の野口通代表は言う。
「私たちのクラブには、まだまだ自分の思ったとおりにプレーのできない子もいます。
でも、だからといって、上手い子を中心にして試合をしていてもチームは強くはなりません。
ではどうするかというと、今はまだ芽の出ていない子も積極的に試合に取り組めるようにしてあげると、だんだんとサッカーが楽しくなってきて『追いつけ、追い越せ』と伸びてきます。
すると今度はレギュラーだった子も負けまいと頑張りますから、相乗効果でチーム全体の力が上がってくるのです。
だから、チームが強くなりたい、優勝したいのならば、すべての子どもたちができるだけ多くの試合を体験できるようにしたほうがいいのだと思います」
[amazonjs asin=”4072959006″ locale=”JP” tmpl=”Small” title=”超カンタンにわかる! 少年サッカールール 8人制サッカー、フットサルもバッチリ!”]
子どもの成長には差がある。今は力を発揮できない子でも、あるときグッと伸びることがある。だから、どの子も試合の出場機会は均等に与えなければならない。
せっかくの土日にサッカーにきても、試合に出ることができず、ベンチで膝を抱えて砂をいじっているだけでは、サッカーが上手くなるはずもないし、面白くなるはずもない。
「サッカーが楽しい!」という気持ちを持たせてあげるのは、ジュニア年代の指導者の大切な使命であろう。
参照サイト:ジュニアサッカーを応援しようコラム「4種(小学生年代)で本格化するリーグ戦がもたらすものとは?」
最後に
2015年度より大幅な改革へと踏み切った少年サッカー界。
いままでの流れと変わったことで指導者など関係者にとっては慣れるまでは少し混乱する1年となりそうですね。
しかしU-12世代の子どもたちにとってはがむしゃらにサッカーに打ち込める環境があれば、今までより更に成長へと繋がるのではないでしょうか。
この改革が少年サッカー界にとって大成功となることを願います。