 2021年8月25日。
2021年8月25日。
秀岳館高校の寮生徒にコロナ陽性者が2人出ました。
そのあとのPCR検査で陽性者は105人にも及びました。
しかし、「クラスター」と名付けられたそれは実質たったの2週間で収束を告げました。
重症者はゼロ。
なぜそんなに速い収束が可能だったのか。
そこには現場を預かる先生たちのすさまじく速い判断と、学校(理事長・校長)とサッカー部の情報の共有・連携の強化がありました。
日頃から生徒と一緒に寮生活を送る寮監でもあり、秀岳館高校の校長補佐でもあり、男子サッカー部の監督でもある段原一詞監督に全容をインタビューしました。
2021年8月13日~15日、帰寮。

その日まで夏休みだった寮に、生徒が戻り始めました。
全国から生徒が集まってきている秀岳館高校サッカー部の寮に帰るのに、今年はワンクッションがありました。
寮生全員のPCR検査です。
段原監督
「全国的な状況があまりよろしくなかったからですね。緊急事態宣言が出ていた地域に里帰りしていた選手もいます。
なので、寮に帰る前に全員PCR検査をして陰性証明を取ってもらいました。
寮にも一斉には選手を入れません。密を避けるため、分散帰寮を実施しました。
陰性証明を取った選手から帰寮させ、トレーニングを再開しました。
ですので、寮に帰ってきた選手はその時点では全員陰性でした。」
全国的に感染者数が爆発的に増えた8月。
東京都では1日10,000人に迫る陽性者が出ていました。
8月23日、体調不良者発生。
2人の体調不良者が出たのは、8月23日のことでした。
段原監督
「学校ですから、体調不良は日常的に発生します。
冬はインフルエンザ、夏はプール熱、そのほか、疲労による風邪など、日常的に体調不良は起きうる環境です。それは子どもも親も指導者も関係ありません。
僕たちは寮にいるので、寮の場合の体調不良が出た場合は、まず1番に隔離をします。
校医さんに診察をしてもらい、薬を処方してもらい、飲ませる。
症状によって様子を見る。
体調が改善したら自分の部屋に戻す。
大きな病院に連れて行く必要がある場合は連れていきます。
普通の親御さんがやっていることと同じことをやります。
幸い、このときは2人の熱はすぐに下がって元気になりました。
いつもなら熱が下がったら少し様子を見て部屋に戻しますが、昨今はコロナの問題があるので念のため、25日の朝に2人を病院へ連れて行きました。
そこで2人に抗原検査を受けてもらったら陽性だったんです。
抗原検査の場合、過去にコロナに感染していると陽性になることもあります。
八代市の保健所と連携し、寮生全員の安全のため、本来なら濃厚接触者のみが受けるPCR検査を寮生全員に対して行いました。
ウイルスの出所はわかりません。
ですが、そのとき私たちに出来ることは理由を解明することではなく、一刻も早く収束させることでした。」
8月25日、ゾーニング開始・完了。

25日の朝、2人の抗原検査が陽性を示したあと、秀岳館高校はすぐにゾーニングを行いました。
まず、グリーンゾーンとレッドゾーンを分けました。グリーンゾーンは感染の可能性のない生徒やスタッフを集めたゾーン、レッドゾーンは濃厚接触者やその他感染の危険があると考えられる生徒やスタッフを集めたゾーンです。
ここから理事長・校長・サッカー部スタッフの情報の共有と連携の強化が始まりました。
グリーンゾーンは、理事長・校長がコントロール、レッドゾーンは、サッカー部がコントロールすることにしました。理事長・校長とサッカー部スタッフは、早朝・朝・昼・夕・夜と一日5回緊密に連絡を取りました。
グラウンドの近くにある合宿所が快く引き受けてくれたため、陽性者の中の無症状の生徒は合宿所に隔離。
寮内には陰性者のみを残すことにしました。
陽性者の中で体調が悪いものはホテル療養の受け入れ体制を。
保健所の指示を待つことなく、サッカー部の監督たちを中心として即座に判断しての実施でした。
これを完了させたのが、もう20年寮内に住み込んで生徒指導に直接当たっている段原監督です。
「僕たちは大事なお子さんを預かっています。
コロナが流行し始めたときから、政府の分科会の資料や感染症の専門家の資料を読み込んでいました。その中にゾーニングの必要性、有効性を示した文献がありました。
頭の中の危機マニュアルに入れてあったものが即座の判断に役立ったということだと思います。
合宿所に電話して使用許可を取り付け、ホテルにも連絡して受け入れ体制を整えてもらい、サッカー部のスタッフに協力してもらってゾーニングを完了しました」(段原監督)
保健所の指示を待たないゾーニングです。
指示を待っていたら感染が拡大するかもしれない。
ですが、一教員の一存で大規模なゾーニングを行うことはできない。
段原監督の背を押したのは理事長・校長でした。
「現時点で少しでもいいとわかっていることがあれば、やったほうがいいでしょう。
最後には俺が責任を取る、やりなさい」
PCR検査の結果がわかるまでには、約1日かかります。
26日、27日に結果がわかり次第、生徒たちはそれぞれの状態に合わせて速やかに隔離を完了しました。
同時に行ったことが、保護者への情報の共有と連携の強化です。
保護者には文面だけではなく、動画を配信することでより強いメッセージの発信を行いました。
実際にサッカー部監督で校長補佐でもある段原監督が保護者に向かって語りかけた動画配信。
状況の報告と連携強化のお願いを即時配信したことにより、保護者たちの反応は顕著に変わりました。
「保護者のモラル向上に感謝」
実は段原監督には、苦い記憶がありました。
5年前の熊本地震のときのことです。
「熊本地震の発生は夜でした。
僕たちは安心安全に生徒を預けて欲しい、と常日頃、こういう体制で生徒を守ります、ということを発信していたつもりだったんですが、
地震の翌日、夜明けとともに寮を出たら寮の前に車の列がありました。
保護者の方が行列をなして生徒さんを迎えに来ていたんです。
遠方の子たちは親同士で連絡を取って、代表の親御さんが車で来て、という感じで。
そのとき僕は非常にショックを受けました。
僕たちはこんなに信用されていないのか、と。
安心して生徒を預けてもらっていなかったんだとそのときわかりました。
僕たちは生徒の安心安全を守るための努力は日頃から行っています。
それをわかってもらう努力が足りなかったんだなと思いました。
そこからの5年間、僕たちにできることを精一杯やると同時に、保護者との情報の共有を大事にしてきました。
連携も強化し、保護者会、後援会などの組織も立て直してきました。
もちろん、地震とウイルスは全然違うものです。
ですが今回、コロナのクラスター発生に関して、学校に保護者の方の連絡も、クレームも来ませんでした。
5年前に大パニックになっていた保護者のかたがたは、この騒動は冷静に学校の判断を尊重し、僕たちに生徒を任せてくれたんです。
それが僕にはとても大きな喜びでした。」
サッカー部が発信する動画のメッセージは収束までに4回発信されました。
1回目は陽性者が出たその日。
2,3回目は寮生全員に対して行われたPCR検査結果が次々にわかった日でした。
報道よりも速く、肉声で伝えられるメッセージ。
それは保護者の安心感を喚起し、スタッフたちは電話対応に忙殺されることなく、全員が全力で生徒たちの対応に当たることができたのです。
早い収束を助けた「モラル」

サッカー部のスタッフで、陽性者が出たときに学校にいたのは10数人でした。
そのうち、行動記録を洗い直して「濃厚接触の可能性が高い」と思われたのは段原監督を含めた8名でした。
濃厚接触の可能性がすでにある、と思われた8人以外のスタッフは寮に入らず、自宅から通っていた陰性の生徒の対応に当たってくれました。
8人はそのまま家に帰らず、自らも隔離された状態で生徒の世話を行いました。
陽性者といっても、3分の1は全くの無症状だった選手たち。
郵便物を届けたり、家から届く荷物を届けたり、日々の食事を届けたり、という日常の世話をスタッフがまるごと行ったのです。
「陽性者、陰性だったが濃厚接触者、陰性の寮生、と区分けして、全部にLINEグループを作りました。
接触できないので、各部屋の前に食事を置いたら『食事を届けたよ』、子どもたちも食べたら扉の前に食器を出して『食べ終わりました』と連絡させて。
お風呂もトイレも同じです、絶対にこれ以上感染を広げないための管理でした。
ホテル療養の子たちにも、普段は『あんまり食べるな』と教えているラーメンを差し入れたり、お菓子を差し入れたり。それは喜んでましたよ」
寮の厨房は閉鎖されました。
給食のスタッフには別の場所でお弁当を作ってもらい、スタッフが取りに行って分配しました。
「食事はお弁当形式になりました。給食のスタッフを寮内に入れなかったからです。
食事が弁当食になったことで、生徒の中に(食事量が)足りる、足りないという話が出始めたんです。
弁当食になると自由におかわりが出来なくなりますからね。
彼らは食べ盛り。
ですが、練習しているのならばともかく、練習していないのにいつもと同じに食事をしたらその後戻すのが大変なことになります。
足りないといっても、必要十分な量や栄養はちゃんと確保してもらっていました。
なので、3度目の動画配信の時に「(食料を)奪い合えば足りない、分け合えば余る」という話をしたんです。それがみんなに深く刺さったようで、そういう騒ぎはなくなりました。
無症状の子たちも、14日間部屋に缶詰になります。
部屋から出るときはトイレであってもLINEグル-プで申告しなければなりません。
そんな感じですから、ルールを逸脱する子も出てくると予想していました。
しかし、ルールを逸脱する子、自分勝手に振る舞う子はひとりもでなかったんです。
秀岳館の生徒のモラルの高さも育っているなと感じました。
1人でもルールを破る子が出たら、きっとこの隔離は長引いたでしょう。
収束が早かったのは、子どもたちのモラルの高さとも関連していると思います。」(段原監督)
感染の可能性がすでにあるとされていたスタッフ8名のうち、そのときまでに6名がコロナ陽性になっていました。
「陽性になったスタッフは、陽性の子どもたちを集めたゾーンで子どもたちの世話をしてくれました。
つらかったと思いますが、責任感と使命感だけでのりきってくれました。」
このとき、途中で陽性になり、陽性者のゾーンに移動したコーチはこう振り返ります。
「自分が陰性だったときは、発熱者を病院に連れて行ったり、食事のグループの面倒を見たりしていましたね。陽性になってからは陽性者の隔離されているところに一緒に入りました。熱や倦怠感があったんですが、動けないほどではありませんでしたので食事の世話とかをそれまでと同様にしていた感じですね。
生徒の世話は僕たちの中では当たり前、特別になっていることは何もありません。この一連のことは、誰も体験したことがないことですから、スタッフみんなで話し合ってどんどん動いていきました」(中嶽直樹 高校男子コーチ)
陽性者は順調に回復していきました。
9月1日、最初に陽性になった子たちが回復して戻ってきました。
それは収束の兆しでもありました。
9月6日、練習(部分的に)再開。

10日間の療養を経て、回復した次々に生徒たちは戻ってきました。
9月1日には2人に減っていたスタッフの疲労のピーク時に、「手伝います」と申し出たのが彼らでした。
105人の大型クラスターが収束を迎えようとしていました。
「保健所のカウントで、症状が出たときから10日間は完全隔離の療養期間です。
8月25日に陽性になった子は22日からとカウントされ、9月1日には戻ってきました。
その子たちが手伝いに入ってきてくれたんです。
陽性になった子は症状の発生から10日間。
濃厚接触者になった子は接触した日から14日間。
それが保健所に定められた隔離期間でした。
どんどん帰ってきて、9月6日から段階的に練習を開始しました。
寮の部屋にこもらせていた子たちでしたから、まずは体作りから。
寮生と自宅生は練習をしばらく分けていました。一緒に練習させるようになったのは10月の初めからです。
最後の陽性者1名が出たのが9月11日。
そのときの濃厚接触者は1名でした。」
9月下旬に、いくつかのマスコミが秀岳館高校サッカー部のクラスターを取り上げ、報道しました。
秀岳館高校の電話は鳴り響き、職員が対応に追われました。
「こっちはもう終わりつつあったのに、まだクラスターが続いているような印象を不特定多数の大勢に与えました。
マスコミで興味本位に取り上げられることにより、生徒も保護者も不安にさせてしまったのが今でも非常に遺憾です。
そのとき隔離されていたのは陽性者1人、濃厚接触者1人でした。
最終の濃厚接触者の1名の隔離期間が明けたのが9月25日でした。
そこで保健所から収束宣言が出ました。
体調不良者が出てから33日、陽性と診断されてからちょうど1ヶ月でした」
9月25日、収束宣言。
最後の隔離生徒が帰ってきたのは9月25日。
翌26日に八代保健所から終息宣言が発表されました。
コロナ陽性者が確認された最初の段階で「感染のリスクがある環境にいた」とされた8人のスタッフの中で、常に先陣を切って対応をしつづけたのは段原一詞監督と矢野君典監督(女子サッカー部監督)です。2人はコロナウイルスに感染することなく、収束まで最前線で生徒たちの対応に当たりました。
段原監督
「収束まで持って行けたのは矢野監督の働きが大きかったと思います。冷静に判断、指示をしてくれました。最後まで無事でいてくれてよかった。
他のスタッフも、次々と陽性になって隔離されていった中、隔離された先でもみんなそれぞれに精一杯のことをやってくれた。彼らの努力なくしては収束はありえなかったでしょう。
生徒や保護者のモラルの高さにも助けられました。
誰か一人が勝手なことをしてしまったら、こんな早い収束はなかった。
すべての人に感謝します」
完璧なゾーニング、それにすべての人員が協力することによって、秀岳館高校サッカー部のクラスターは最短とも言える期間で収束を迎えました。
「誰も現状逃避しようとしなかった。これが大きいと思います。
有事のときこそ、その人の人格が出ます。
ひとつ間違えば大パニックになるような、こんな事態を保護者も生徒もスタッフも冷静に対応してくれた。保護者の方はこちらの方針を信じ、任せてくれた。
5年前とは明らかに違う対応を体感し、本当に感謝しています。
誰かがルールを「自分だけだから」と破ってしまったら、そうした心の甘さがあったら、まだ収束していなかったかもしれません。選手権を目の前にして、今まで以上に一丸となれた秀岳館サッカー部を実感しています」
文字通り全員で切り抜けたクラスター。
「なぜ監督は感染しなかったんだと思います?」という問いに、段原監督は笑いながら答えました。
「よくわかんないです。
自分が感染したら、ここで倒れたら、という恐怖はなかったです。
それ以上に、自分がコントロールタワーにならなければ、という責任感と使命感がありました。
生徒を守らなければならない、やるべきことを今日もやる、という感じで毎日そればかり考えていました。
人がいれば必ずいろいろな感染症は入ってきます。
それはインフルエンザでも同じですよね。
インフルエンザを一人も出したことがない学校なんてないでしょう。
今年のインターハイも、全国的に見たときにいくつもの学校が陽性者を出して棄権せざるを得なくなったところがありました。
誰にでも、どこにでもあるリスクなんです。
僕たちもいつかはこうなるかもしれないという事態に備え、勉強と情報収集はかかさないようにしていました。
今回も、事前に受け入れをしてくれるところをリサーチしてありました。
その結果迅速に対応ができ、被害も最小限だったのなら本当に良かったです。
正しい知識を得る努力と迅速な判断をこれからも心がけて行きたいと思います。
コロナ陽性発生当初から『最後は、俺が責任をとる』と言ってくれた理事長・校長には感謝しかありません。この地方八代で105人におよぶクラスターですからね。その胆力のおかげで僕もスタッフも自分の役割に徹することが出来たと思っています。ありがとうございました。」
お話を聞かせてくれた人

段原 一詞 [Kazushi Danbara]
1997年 高知県明徳義塾高校サッカー部監督
2001年 熊本県秀岳館高校サッカー部監督
明徳義塾高校監督時代に1度、秀岳館高校監督時代に1度(2020年現在)、全国大会にサッカー部を導いている。※
輩出したJリーガーは2021シーズンロアッソ熊本加入のターレス選手、ケンタ選手で11人目になる。
秀岳館高校校長補佐。
※明徳義塾 全国選手権1度(初出場)インターハイ1度(初出場)四国大会3度
秀岳館 全国選手権1度(初出場)九州大会3度
関連記事
スペインへの挑戦を育てた指導 代表歴なしの女子がスペインリーグに見いだされるまで(秀岳館高校女子サッカー部 矢野 君典監督インタビュー)
https://green-card-news.com/post-982222

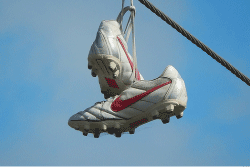
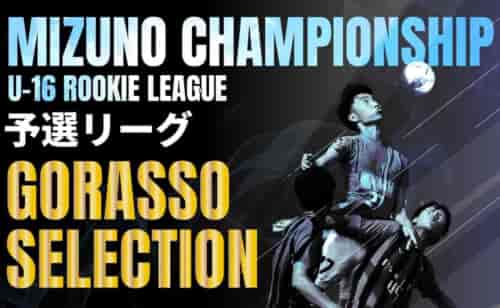



コメントはまだありません。