
体が開くとは?サッカー指導者が気付かない育成期の弊害
 サッカーで体が開くと、ドリブル、キック、トラップなど全てのプレーのパフォーマンスが著しく低下します。
サッカーで体が開くと、ドリブル、キック、トラップなど全てのプレーのパフォーマンスが著しく低下します。
ところが、日本の少年サッカーの指導者たちは、子供たちの体が開くような練習ばかりさせています。
一方、格闘技、野球、ゴルフなど、ほぼすべてのスポーツで、パワーとスピードを一点に集中させるために体の開きを抑えています。
そうした意味では、サッカーの練習においても、特に幼少期から正しいトレーニングを続けることが大切です。
そこで、今回はサッカーで体が開くことの意味や開きを抑えるための練習法などについて解説します。
1.体が開くとはどういうことか?
(1)体が開いた状態とは
体が開くとは、両足を揃えた棒立ちの姿勢で左右の胸が正面を向いた状態です。
これに対して、体が開かないとは、左右どちらかの肩と足を前に出した、いわゆる「半身」の状態です。


ヒトが日常生活の中で立った姿勢を維持する時は、もともと体が開いています。
その理由は、両手と両足が体の側面にあって胸が正面を向いているからです。
また、日常生活では立っていても座っていても、基本的にはこのような姿勢を維持しています。
だからと言って、特に不自由を感じるわけではありません
ところが、体が開いた状態はサッカーなどのスポーツに向かない姿勢です。
その理由は大きく分けて3つあります。
・パワーが集中できない。
・体の軸が不安定。
・上半身が使えない。
つまり、サッカーなどのスポーツでは、日常生活とは全く違った動きが必要なのです。
その際、体が開くとプレーのパフォーマンスが低下することを意味します。
私の息子の「とも」は利き足でボールを持ち、半身の姿勢を維持しているので体の開きはありません。
例えば、ドリブルなどで体が開く人と開いていない人が対峙する時は、アルファベットの「T」の字になっています。

 これは「股抜きのタイミングは2つだけ!必ず効果が出る練習法とは?」の記事で解説した体勢そのものです。
これは「股抜きのタイミングは2つだけ!必ず効果が出る練習法とは?」の記事で解説した体勢そのものです。
要するに、体の開きを抑えた姿勢を続けないと、十分なパフォーマンスが発揮できないのです。
(2)体が開くとパワーを集中出来ない
体の開きを抑えることで、全身のパワーを一点に集中することが出来ます。
また、パワーアップすることでスピードも十分に発揮します。
こうした一点集中にパワーを発揮させる動作は、全てのスポーツの基本の考え方であり、最も大切なことです。
一方、力を一点に集中させるのは物理学の基礎です。
例えば、カナヅチで釘を正確に真っ直ぐ打つためには、釘の頭を垂直に叩きます。
この時、釘の頭を垂直で正確に叩いてさえいれば、非力な子供でも十分に釘を打ちこむことが出来ます。
なぜなら、釘の頭にカナヅチのパワーを一点集中させているという、力学の基本に基づいているからです。

 サッカーのプレーにおいても、これと全く同じことが言えます。
サッカーのプレーにおいても、これと全く同じことが言えます。
ドリブルやキックでは、身体が開かない状態の方がパワーを一点に集中出来るのです。

 ところが、体が開いた姿勢では、パワーの一点集中は出来ません。
ところが、体が開いた姿勢では、パワーの一点集中は出来ません。
次の画像でも分かる通り、体が開くと100の力を一点に集中するのではなく、右半身と左半身に50ずつ分散してしまいます。

 そうすると、パワーを一点に集中できないので、当然のことですがスピードもありません。
そうすると、パワーを一点に集中できないので、当然のことですがスピードもありません。
例えば、次の動画のようなドリブルは、ボールにタッチしながらも左右の胸とヒザが同じ方を向いています。
これは、身体が開いた棒立ちの状態であり、左右の胸が正面を向いた姿勢です。
こうしたドリブルをいくら続けても、パワーを一点集中させることが出来ませんし、スピードもないので、サッカーの試合では役に立ちません。
(3)体の開きと軸の強さ
① 体が開く場合
体の開きと軸の強さは深い関係があります。
体が開いた棒立ちの姿勢では、上体を支えることが出来ません。
次の画像のように、前から押すとカカトで身体を支えるしか出来ないのです。
また、体の中心軸である背骨周辺の筋肉も働かないので、かなり不安定な状態です。

 ヒトの体には、地球の重力に抵抗して立った姿勢を維持させるための「抗重力筋」があります。
ヒトの体には、地球の重力に抵抗して立った姿勢を維持させるための「抗重力筋」があります。
この抗重力筋はヒトが日常生活で立ったり歩行したりするために使う筋肉です。
 この場合、体が開いた棒立ちの姿勢でサッカーをすると、抗重力筋に依存したプレーが多くなります。
この場合、体が開いた棒立ちの姿勢でサッカーをすると、抗重力筋に依存したプレーが多くなります。
つまり、サッカーというスポーツ対して、日常生活で使う筋肉を働かせるわけです。
特に左右の太ももの前側にある大腿四頭筋がよく使われます。
ところが、サッカーのボールプレーは片足立ちになることが多いので、軸足はもちろん、体の中心軸(体幹)を鍛えてフラミンゴのようにバランスを取らないと的確なプレーが出来ません。
つまり、体が開いた姿勢は軸が不安定になるのです。
② 体が開かない場合
体が開かない姿勢では、軸足と中心軸(腹部や背骨周辺の筋肉)で身体を支えようとします。
また、この軸足と中心軸が強化された人は、常に身体の開いていない半身の姿勢を維持することが容易です。

 私のブログでは「ちょんちょんリフティング」などで軸足の強化を!という解説が多いですが、厳密に言うと軸足だけではなく、体の中心軸にある体幹も鍛えられるのです。
私のブログでは「ちょんちょんリフティング」などで軸足の強化を!という解説が多いですが、厳密に言うと軸足だけではなく、体の中心軸にある体幹も鍛えられるのです。
(4)体が開くと上半身が使えない
体が開く選手は、日常生活でよく使われる抗重力筋に依存したプレーが多くなります。
その場合、最も多く使うのは大腿四頭筋(太ももの前側の筋肉)です。

 この場合、二つの大きな問題があります。
この場合、二つの大きな問題があります。
① 上半身のバネ作用が使えない。
体が開いた選手は、日常生活でよく使われる抗重力筋に依存するため、背骨のバネ作用や体幹ひねりなどのパワーやスピードが発揮できません。
次の画像にもあるとおり、メッシと一般的な日本人のバネ作用の違いは明らかですね。

② 下半身だけでプレーするので上半身が重りになる。
日本の場合は「ヒザのバネを使え!」など、下半身の動作を重視する指導者が多いです。
これでは重たい上半身を下半身の力だけで「よいしょ!」と背負ってプレーするようなものです。
それに上半身と下半身の体重比は6対4で上半身の方が重たいので、身軽な動きは出来ません。
2.他のスポーツに見られる体の開き
ここでは体が開く状態が、比較的分かりやすいスポーツとして、格闘技、野球、ゴルフを例にして解説します。
(1)格闘技と体の開き
格闘技は、お互いに体の開きを抑えた半身の姿勢を取り続けながら試合します。
① ボクシング
ボクシングでは左右の肩、胸、腕の一方を前に出し、もう片方を後ろに下げた姿勢を取ります。


また、体が開かず半身の姿勢を維持していれば、相手のパンチを受けても衝撃をかわすことが出来ます。


ところが、左右の肩、胸、腕が正面を向いた体が開いた状態では、防戦一方になるので反撃出来なくなります。


② 柔道
柔道の場合もボクシングと同じように、半身の姿勢を取ってパワーを一点に集中して攻撃します。
ところが、体が開いて棒立ちになると何も出来なくなるので簡単に投げられてしまいます。


③ 相撲
相撲の場合はやや分かり難いと思いますが、やはり半身の姿勢で体の開きを抑えて攻めます。
次の画像のように、黒のまわしの力士は、左腕、肩、胸を前に出し、右半身を後ろに引くことで体の開きを抑えています。


これに対して、青のまわしの力士は、体が開いたほぼ棒立ちの状態で、左右の胸、腕、肩が揃って前を向いています。
こうなると体の開いた青のまわしの力士は、力を出すことができないので、土俵から押し出されてしまうのです。
(2)野球
野球の場合、バッティングを例にすると、次の動画では「体が開くとは、体の中の力が外に逃げること」と説明しています。
体の中の力が外に逃げる…というのは、先ほど解説した「パワーが一点に集中出来ない」ということと同じ意味です。
また、右バッターであれば、左肩と左ヒザがピッチャーの方を向いてスイングすると体が開いた状態としています(当然、両胸も向いてしまう)。
そうすると、ピッチャーのボールに対して振り遅れるなど、バットスイングも遅くなるわけです。
(3)ゴルフ
ゴルフの場合も野球と同じです。
ボールを飛ばす方向に上体を早く向け過ぎると体が開くので、パワーを一点に集中できません。


3.体が開くのを抑えるためには?
(1)体の開きを抑える意味
サッカーで体が開くと、ドリブル、キック、トラップなどの全てのプレーのパフォーマンスが発揮されません。
先ほども解説したように、格闘技、野球、ゴルフなどの他のスポーツでもパワーとスピードを一点に集中させるために、体の開きを抑えているのです。
そのためには、特に幼少期から正しいトレーニングを続けることが大切です。
最も重要なことは、利き足をメインにしてプレーすることです。
利き足を使うということは、半身の姿勢を維持するので、体が開かなくなるのです。


そのために最も効果的な練習は、利き足のインステップリフティングです。
このリフティングを練習するだけでも、ボールを持つ時の姿勢がかなり改善します。
このリフティングが2~300回くらいを超えたあたりでは、まるで海外のトッププレーヤーのように、体の開きがなくなります。
小学校低学年によく見られがちな、ドタバタした感じの姿勢もなくなります。
ちなみに、ヒトが立っている時は、左右の足で体重を半分ずつ支えているわけではありません。
ヒトの左右の足は、どちらか一方が利き足で他方が軸足として使われます。
そうすると、立っている時の姿勢では体重のほとんどを軸足で支えているのです。
そうした意味では、利き足は正確で素早い動作に使われ、軸足は体全体を支えることが主な役割なのです。
そうした意味では、利き足を使ってサッカーをするのはとても自然なことなのです。
(2)幼少期からの過度な両足練習と体の開き
日本のサッカー指導では、試合で両足が使えるように幼少期から両足練習を繰り返します。
こうした練習は棒立ちで体が開く習慣を身に付けるだけです。
例えば、両足のマーカードリブルや両足リフティングなどの練習は歩く動作と変わりません。
別の意味では、単に抗重力筋を鍛えているだけであって、サッカーで最も大切な軸足や中心軸(体幹)さえも強化していないのです。
また、こうして両足練習を繰り返した子供たちは、特徴的なボールの持ち方をします。
それは、両足の間にボールを置くということです。
こうした状態では半身の姿勢を維持出来ません。
そうすると体が開くことになるので、パワーとスピードを一点に集中出来ないのです。
次の動画では、ほとんどの子供の体が開いていますが、これが日本の少年たちの現実です。
私は、逆足練習を否定するつもりはありません。
幼少期からの過度な両足練習が問題だと考えているのです。
両足練習を始めるのは、利き足のレベルを上げ、全てのテクニックをマスターしてから覚えれば良いと思っています。
一方、近年では土屋健二氏が開発したジンガドリブル(ジンガステップ)が、全国に広まりました。
体を左右に回転したり体幹を使っているように見えますが、この動きはサッカーではあまり意味を持ちません。
ダンスパフォーマンスと同じレベルのものです。
しかも、ボールにタッチしながら、左右の胸とヒザが同じ方を向いています。
これは体が開いた棒立ちの状態です。
こうしたパフォーマンスは、全国の子供たちに大人気のようです。
でも、こうした練習を続ける限り、パワーを一点集中させることが出来ません。
スピード感もなければ、ゲームプレーにも役に立ちません。
こうした点は大人がきちんと理解して、子供たちに正しく教えないといけません。
4.まとめ
これまで、サッカーで体が開く意味をいろいろと解説しました。
特に、サッカーで体が開くと、ドリブル、キック、トラップなどの全てのプレーのパフォーマンスが発揮出来ません。
一方、サッカー以外のほぼすべてのスポーツでは、パワーとスピードを一点に集中させるために体の開きを抑えています。
そのためには、特に幼少期から正しいトレーニングを続けることが大切です。
ところが、日本のサッカー指導では、試合で両足が使えるように幼少期から両足練習を繰り返します。
こうした練習は、日本の指導者が、体の開きを抑えるという正しいスポーツ理論を分かっていないことによる一種の弊害です。
日本のサッカーを本当の意味で強くするためにも、一人でも多くのサッカー関係者に体が開くことの弊害を理解してほしいと願っています。

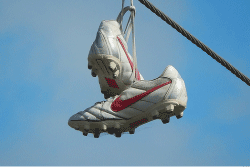
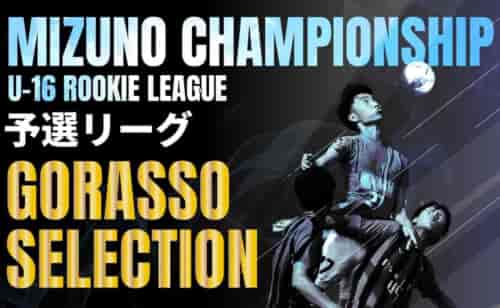



いい加減な記事だなあ
妄想だよこれじゃあ