リオデジャネイロオリンピック・アジア最終予選でU-23日本代表がオリンピック出場を決めた翌日、東京都御茶ノ水にあるJFAハウス(日本サッカー協会)にお邪魔し、山口隆文JFA技術委員長(育成担当)にジュニアサッカーNEWSがインタビューしてきました。
【追記】山口隆文氏は指導者養成ダイレクターに就任しました。
山口隆文技術委員長
山口県出身。高校から国体で3位、筑波大学在学中に第28回全日本大学サッカー選手権大会優勝(主将)。その後、社会人となっても東京都青年の部代表として国体に3年連続出場。卒業後は体育教師として都立東久留米高校の指導等にあたる。川崎フロンターレの中村憲吾選手の恩師としても有名。
photo:つる
リーグ戦には意図がある
 (サッカー通りにあるJFAハウス。こちらでお話をお伺いしました。)
(サッカー通りにあるJFAハウス。こちらでお話をお伺いしました。)
今年度から、全日本少年サッカー大会の進め方が変わり、年間を通してのリーグ戦の結果を反映しての冬開催になったことは、保護者の皆様もご存知の通りです。
改めて、「なぜリーグ戦なのか」から尋ねてみました。
以下、緑字になっているところがジュニアサッカーNEWSの質問です。
リーグ戦を導入したのはなぜですか?
山口技術委員長(以下敬称略)「試合経験を増やし、試合‐練習‐試合の流れを定着させたいと思っているからです。
今までは、弱いチームだとトーナメント一回戦で敗退してしまうことが多かったと思います。ところが、弱いチームにも良い選手はいる。リーグ戦は年間(4月から10月)を通した基軸となるリーグ戦。年間20試合程度をお願いしている。
ジュニア選手の底上げのために、公式戦を戦う機会をたくさん与えたい。
公式戦で試合をして、調整して、また試合をする。その繰り返しは、子どもたちにも指導者にも多くのことを学ばせると思います」
弱いチーム(勝てないチーム)は、公式戦の年間試合数が少ないのが当たり前でした。トーナメントの試合では、1回戦で負けてしまえば終わりです。フレンドリーマッチのような親善試合がその後行われる地域もあるようですが、勝ち負けに真剣になるような緊張感はフレンドリーマッチにはありません。
緊張感のある公式戦の機会を増やすこと。それは、選手全体の底上げにつながるはずです。」
8人制のメリット
人数も、今までの11人から8人に減りました。
山口「人数が減ったことにより、一人一人の判断や運動量は増えています。ただ確かに、出られない選手が出てくるのも当然人数が減ることによっておこる事態だと思います。
JFAは、【補欠ゼロ】を目指したい。試合に出られない子どもがいないように、20人いたら2チーム作ってリーグ戦に出てほしい。
ただし、それには試合会場や運営、審判などのさまざまな問題をクリアする必要はあると思います。
特に東京都などのようなところでは、大会会場の確保だけでも大変です。でも、数年後には、たくさんのチームが複数登録をして補欠ゼロになり、多くの選手が公式戦を戦える状態にしたい」
20人の場合、11人制だと作れるチームは1つです。ところが、8人制にすると2チームできます。そして、「○部リーグ」のように、レベル別にリーグ戦のグループが組めるリーグ戦なら、子ども同士の実力が拮抗した試合ができるようになるのです。
もちろん、今まで試合に出られなかった子も出るチャンスが巡ってきます。
山口「10-0の試合では、負けるチームの子どもたちは楽しくもなんともないわけです。嫌になるかもしれない。見ている保護者の方もそうでしょう。
ただ、自分に合ったレベルのリーグで公式戦の機会を何度も持つことができれば、拮抗した試合ができる。見ているほうも面白いですよ。やっている本人たちも、もちろん面白いはずです」
その子に合ったレベルのところで公式戦をたくさん行うことができる。今まで公式戦には出られなかった子が、公式戦で刺激を受け、日常のチーム練習をしてその成果をすぐに試合で試せるようになるのです。」
指導者に求められること
 photo:Mark Maybell
photo:Mark Maybell
複数登録をすると、指導者の数も必要になるのでは。
山口「指導者の質を上げることも当然必要になってきます。現在、日本サッカー協会では、チームに最低1人はD級コーチがいないと登録できないようになっています。
ところが、監督1人がD級コーチで、実際にピッチに立っているコーチは無資格ということも起きている。それを防ぐために、実際に指導に当たるコーチにもD級講習会を必ず受けてもらいたいと思っています。
D級コーチの資格は、二日間の講習会で取れるようになっています。良い指導者が増えることは、良い選手を育てるために欠かせません。
指導者の技量は子どもの技術にも生きてきます。海外では10歳以下の選手のヘディングは脳や頸椎に影響を与えるとして行われない地域もあるようです。日本でも、そんな風潮がある。でも、柔らかいボールで行えば、怖がらずに子どもでもヘディングができますよね。
子どもには難しい、ということがあっても練習方法を変えたり頻度を変えたり、さまざまな工夫によってサッカーの練習を行うことはできます。それには、やはり指導技術というものが大事になってきます」
サッカーチームに子どもを預けるというのは、ピッチ内のコーチはすべて指導者に任せるということ。そのためには、良い指導者、良いチームを選ぶ目が保護者自身にも必要になってきます。
「良いチーム」の見分け方
 photo:HolgerLi
photo:HolgerLi
良いチーム、良い指導者を選びたいと思う保護者は多いはずです。どんなところを見れば良いチームを選べますか?
山口「今は、チームを選択できる時代になってきていると思います。自分の息子がサッカーを始めるとき、僕は市内のサッカーチームを全部見て回りました。そして、思うチームに出会えなかったので自分でチームを作りました。
親がサッカーにおいて子どもにしてやれることは、チームを選んであげることだけです。ぜひ、事前にチームの調査をしてください。ホームページを見れば、情報更新の速度が分かります。保護者会があるか、欲しい情報があるかはそこで分かりますよね。実際に見に行けばもっといろいろなことが分かります」
親が子供にしてやれることは、そう多くありません。サッカーにおいては、チームを選んであげること。指導者は、子どもが小さければ小さいほど重要なものになってきます。
山口「まず、親が正確な情報を持ってください。どんなことが選手を育て、どんなことが選手をつぶしてしまうか。
指導者が子どもをダメにしてしまうこともあるし、保護者の過介入がよい選手をつぶしてしまうこともあるのです」
「自分の子どもの能力を見極めて」
 photo:Chris Tse
photo:Chris Tse
親が子供にしてやれることは、ほかにどんなことがあるでしょう?
山口「先ほどの話とも関係してきますが、自分の子どもの能力を見極めるということです。
ヨーロッパのチームなどでは、上手な子どもが3部リーグくらいでプレイしていると、次のシーズンは2部や1部のチームでプレイしているということが起こります。
日本はまだまだそういう文化はなく、チームを代わると「裏切り」とか「捨てた」と表現をすることもあるようです。が、チーム間の移動のような狭い価値観にとらわれないでいただきたい。
その子にマッチした場所でプレイさせてあげるのが、親にできることです。自分の子は今どこでプレーするのが良いか、それを見極めてあげることがその子の成長にも良い結果になると思います」
能力を見極めることは難しいのでは。
山口「親が自分の夢を子どもに預けて子どもをつぶす例も多くあります。プレイヤーズファーストという言葉がありますが、本当に自分の子どもがいきいきとプレイするのはどこがいいのかというのは、子どもを見ればわかると思います。
過度な期待をするのではなく、今の子どもを見てあげればよいと思います。子どもはどんどん変わりますから、それに合わせてチームも自由に変えていっていいと思う。
努力する子は伸びるし、伸びたらまた一段上でサッカーをして刺激を与えていくことが成長につながると思います。既存の価値観にとらわれず、子どものことを一番に考えてほしいです」
能力よりもはるか上のチームを選んで、大会にも出られないままベンチを温めているのと、実力相応のチームで公式戦に出て、似たような実力のチームと勝った負けたを繰り返すのと、どちらがゴールデンエイジのジュニア世代によっていい結果を導くかは歴然です。
ジュニア年代は、教え込むことによってチームが強くなったりする年代です。が、ジュニアのころに「自分で考える」癖をつけなかったら、3年後、5年後はどうなっていくでしょう。
教え込むことの弊害についてもうかがいました。
ジュニア選手の自立のために
 photo:David K
photo:David K
今年の全日本少年サッカー大会では、ハーフタイムに選手だけでミーティングをするチームもありました。
山口「JFAは、そういう選手主体のチームが増えることを望んでいます。
ジュニア年代のうちに、勝利を何よりも優先させてしまうと、答えを先に教えてしまう指導者も出てくる。その方が早く勝てるようになるからでしょう。
ただし、それには問題があります。自立した選手を育てるには、自分で考えるということが必要です。自分の意見をしっかり持っていて、それを論理的に説明できる選手が育つ土壌を作るためにも、問題を自分たちで解決するという姿勢を育てたい」
アンダーカテゴリーの海外の代表選手と日本の代表選手には歴然とした差があるといいます。それは、大人から何か質問されたときと、何か問題が起こったとき。
日本の中学生年代は何か問題が起こった時、大人に言う選手が多いそうです。それは報告だったり相談だったりするのだと思いますが、海外の代表選手は、大人の手を借りずに自分たちで解決しようとする。海外と日本の差を埋めるためにも、オフ・ザ・ピッチ、ピッチ外の振る舞いが大事になってくるのです。
自立した選手は、ピッチの中だけでは育ちません。家庭の果たす役割も大きいものです。自立した選手を育てるために、保護者のできることは何でしょう?JFAでは、保護者や指導に関わる人の理解を深めるために、キッズリーダー講習会を開いています。
公認キッズリーダー養成講習会
2015年度の夏に行われたトレセンでは、保護者向けにJFAが行う研修会がありました。
トレセンにわが子が行かなくても、保護者がサッカーというもの、育成というものをより深く理解するためのJFAの取り組みがあります。
それが、キッズリーダー制度です。
キッズリーダー講習会は、指導者でも、保護者でも、満16歳以上ならだれでも参加することができます。
公認キッズリーダーは、「10歳以下の選手・子どもたちに関わる指導者・保護者等で体を動かすことの楽しさを伝える指導者の育成」(引用:JFA HP)を行うためのものです。
トレセンは「個を育てるため」
 photo:Denise Krebs
photo:Denise Krebs
ジュニア選手に与えられているチャンスとして、トレセンがあります。トレセンとは、なんのために行われているのですか?
山口「トレセンは、天井効果を排除し、選手により強い刺激を与えることにより、選手個人を育てるためのものです」
天井効果とは?
山口「サッカーは一人でやるものではありません。うまい選手でも、一人でチームを勝たせることは難しい。
うまい選手にもっと刺激を与えて持っている能力を伸ばすには、もっと上手な子たちの間でサッカーをさせてあげるのが一番です。そこで刺激を受けてもっと上手になれる。
トレセンに選ばれた選手は、【個を伸ばすチャンスを与えられた】ということです。トレセンは何かのゴールではありません。トレセンは手段です。トレセンを使って、自分がもっともっと伸びるチャンスを与えられたということにすぎません。」

トレセンはゴールではなく、自分がもっと光る選手になるための手段なんですね。
山口「手段です。目的ではありません。試合も、大会も、個人が伸びるための手段です。
チームとしての勝利のモチベーションと、個人の目標のモチベーションは混同されがちですが、試合やトレセンを上手に使って【自分が伸びるための努力】をする選手がたくさん出てきてほしいです」
まとめ
 JFAが今年度から取り組んでいる「通年リーグ、8人制サッカー」の後ろには、
JFAが今年度から取り組んでいる「通年リーグ、8人制サッカー」の後ろには、
・公式戦の機会を増やす
・リーグ戦導入により、同じレベルの子どもたちと拮抗した試合をする機会が増える
・補欠ゼロ、全員が公式戦をたくさんこなせるチャンスを与える
という意味合いが含まれています。
個人が強くならなければ、日本サッカーの展望はありません。そのために、
・大会も、トレセンも、「個人が伸びる」チャンスを与えるものである
・保護者も、指導者もともに理解を深め、よい才能を育てていく必要がある
・適切な指導を受けるために、親はチームをよく選ぶ
ということが必要になってきます。
山口「わかること、できることは真の喜びです。身体を動かしたいという運動欲求、仲間と一緒にやりたいという所属欲求をかなえ、一人では勝てないことを教える。それがチームスポーツの価値です」
日本サッカー協会は、ジュニア選手の保護者が知っておきたい情報を、ホームページで公開しています。
日本サッカー協会(JFA)のホームページはこちら
日本サッカー協会の普及の取り組みは「サッカーファミリー」から、
育成に関する試みは「選手育成」のタブからご覧ください。
山口技術委員長から保護者の方々へのひとこと
子どもたちを見守り、子どもたちの「ベストサポーター」でいてください。
最後に
「8人制だと出られる選手が減ってしまうのでは?トレセンに行けない子にもチャンスは与えられないか?日本サッカー協会がジュニア年代の保護者に望んでいることは何なのだろう?」という思いでJFAハウスを尋ねました。
トレセンへ行けば輝く選手にしてもらえるわけではありません。地域で輝いている子の中からトレセンでさらに自分を磨くチャンスを与え、その子たちの中からさらに輝く選手を育てる…というピラミッドの先の頂点に日本代表がいます。
山口技術委員長の話を聞いていると、日本サッカー協会がジュニア選手の育成に本気で取り組んでいる気迫が伝わってきました。こんなに打つ手があるのなら、日本のサッカー界は絶対もっと強くなると確信させられました。

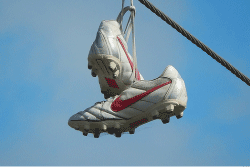
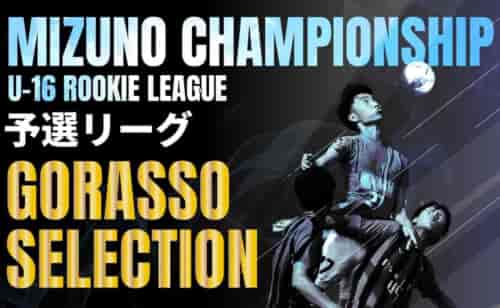




コメントはまだありません。