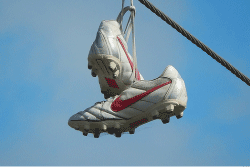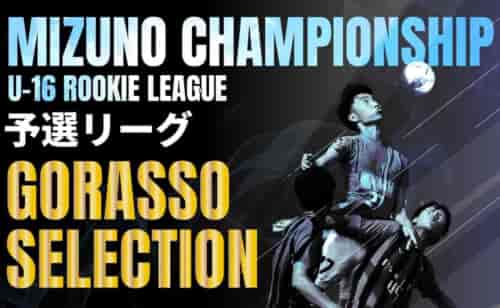将来、子どもたちの職業の選択肢になるかもしれないサッカー選手以外の裏方の職業についての第7弾です。
実業之日本社から出ている『サッカーの憂鬱』(能田達規著)をテキストに、サッカーの裏方の職業をシリーズでお届けします。
今回は通訳(監督通訳)についてです。通訳という職業について、少し深く掘り下げてみましょう。
「子どもたちに知って欲しい!」シリーズのバックナンバーまとめはこちら!
photo:Ronnie Macdonald
CASE.7 あらすじ
場面はベンチです。審判の判定に不服を言い募る監督を通訳が抑えようとしています。
このあと、通訳は負傷退場。監督の振り回した手が通訳に当たったためです。
通訳は24時間勤務?
日本代表の監督に外国人監督が就任することがありますね。すると、必ず監督の通訳が付くことになります。
外国人監督は、別に日本語を勉強して日本にやってくるわけでもなければ、日本愛好家で文化に精通しているわけでもありません。
どうしてもつきまとう言葉の壁を低くし、選手やスタッフとの意思疎通がスムーズに行えるようにするのが通訳の仕事です。が、言葉の壁は別にピッチ内だけにあるのではありません。
監督の日常にも言葉の壁はいつも付きまといます。監督の日常がある限り、通訳は必要だという場面が生じるのは当然です。
これは、選手でも同様です。選手の中でも個人差があり、日本語を積極的に取りいれていく外国人選手と、全く取り入れる気のない外国人選手がいますが、最初はだれもが同じく、日本語は分からない選手がほとんどです。
ピッチの中だけでなく、日常のサポートも必要となるのは外国人選手も監督の場合と同じです。
通訳なのか、パーソナルアシスタントなのか
『サッカーの憂鬱』の中でとりあげられている、「通訳が呼び出される」という場面を列挙してみます。
・マンションの住人とのトラブル
・散髪
・喫茶店探し
・インターネットのトラブル
「これじゃ、パーソナルアシスタントだ」と通訳がぼやく場面もありますが、実は通訳の仕事はそのとおり、パーソナルアシスタントなのです。
監督が仕事をしている時は、常に通訳も仕事中です。元日本代表監督のイビチャ・オシム氏の通訳をしていた千田さんは、オシムさんが大好きだったカードゲームのときもずっと横にいて通訳をしていたそうです。
監督が選手と話をするときも、
会議に出るときも、
プライベートで外出するときも、
監督の日常を快適にし、来日してもらった目的のために全力を発揮してもらえるようサポートする。それが通訳の大事な仕事なのです。
家族が来日すると、家族のための通訳をすることもあるようです。まさにパーソナルアシスタントの資質を持っていないと監督の通訳は務まらないと言ってよいでしょう。
通訳が握る監督の「成否」
通訳は「かけはし」
通訳が訳すのは、監督の言葉だけではありません。監督の周囲の日本人の言葉も訳して伝えなければなりません。
「後ろのドアから入らないで」という言葉と、
「前のドアから入って」という言葉は、言っていることは全く同じですが印象が違います。前者は「禁止」、後者は「指示」です。
内容は同じでも、前者を言われたら、「きつそうな人…」と感じてしまうかもしれません。すると、第一印象としてマイナスの感じを与えます。マイナスの感じを与えてしまったら、プラスに転じるのには時間がかかってしまいます。
監督を取り巻く人たちの中で、よりよい人間関係を監督が築くために、通訳者は高いコミュニケーション能力をもって「かけはし」にならなければならないのです。
ザッケローニ監督就任会見事件
わからない外国語を話された場合、私たちは当然「通訳の言葉=監督の言葉」だと思います。
ところが、「通訳が監督の言ったことを十分に訳さなかった」「違うことを言った」「言ってないことを通訳がしゃべった」ということは、結構よくあることのようです。
ザッケローニ監督の就任会見も話題になりました。「(アジアカップでは)絶対的な主役を演じなければならない」とイタリア語で答えたザッケローニ監督の言葉を、通訳者が「トップ3を狙わないといけない」と訳したのです。
ザッケローニ監督は、トップ3を目指すとは一言も言っていません。代表監督の会見は、今後の日本代表の方向性を位置づけるもの。これは大きな違いでした。
「トップ3をめざす」という通訳の言葉しか聞こえない私たちの中には、アジアカップでトップ3を取れなければ「言ったこともできないのか」と思う人もいるでしょう。それが監督への不信感につながることもあります。選手も同様です。
通訳の出来が監督の仕事の出来を左右する
監督と通訳の齟齬が広がれば、私たちが監督に対して不信感を抱いてしまう原因になるのです。監督の覚えのないところで聴衆が、または選手が監督に対して不信感を抱くことは監督の仕事に対して明らかなマイナスです。
外国人監督の成否は、ほとんど通訳にかかっていると言っても言い過ぎではありません。監督の意思が十分に伝わらず、また、選手やスタッフの意思も監督に十分に伝わらなければ、コミュニケーションに支障が出ます。
コミュニケーションが滞った場合、監督がどんなに素晴らしいものを持っていても発揮することができません。厳しい言い方をすれば、外国人監督が力を発揮できない場合は、それは通訳の責任という可能性もあるということです。
監督を守るための「意図的な誤訳」
通訳は時に、意図的に監督が言ったことと違うように訳したり、周りの人間の言葉を故意にニュアンスを変えて訳したりすることがあります。これは一概に悪いこととして片づけられない側面があります。
監督の眺めている雑誌には監督をけなした記事が載っています。「これはなんて書いてある?」と聞かれたら?
監督が感情にまかせて吐き散らした暴言を、選手に「なんて言ってるんだ?」と聞かれたら?
そんなときに発動するのが「意図的な誤訳」のようです。それをそのまま監督に伝えるのはまずい、選手に伝えるのはまずいということを考えた時に、意図的にオブラートにくるんだり、意訳したり、事実に反しない範囲内で誤訳にすることは「あり」だということです。
一番に追求しなければならないのは、監督の利益です。利益というと語弊があるかもしれませんが、監督が持っている力を十分発揮できるように、ということを第一に考えなければなりません。
マスコミで監督が傷つかないように。自分の訳で選手と監督の仲がこじれないように。この鍵を握っているのが通訳なのです。
サッカーの知識ももちろん必要
戦術論を監督が語るとき、それを十分に理解していない通訳が訳すとどうなるでしょう。
すぐれた戦術論でも、分かりやすい日本語に置き換えて選手に伝えることができなければ、チームは機能できず、大混乱になるでしょう。監督への不信感を募らせてしまう原因にもなるかもしれません。
それには、教科書で外国語の勉強ができるだけではだめなのです。その国の言い回しやニュアンス、また、サッカーの戦術や技術に関してわかっていなければ、適切な日本語に直すことはできません。
これは、選手の通訳でも同じです。
日本人選手が「マノン!」と叫ぶと同時に、通訳が「ラドロン!」と訳せなければ、ブラジル人選手には通じません。
サッカー用語を知り、その国のサッカーの特徴も知っていて、なおかつサッカーの戦術等についても深い知識を持つ人でないと、監督の通訳は務まりません。
さまざまな通訳たち
フィリップ・トルシエ監督の通訳
元日本代表監督のフィリップ・トルシエ監督は、記者会見の際などの公式の場の通訳とチーム内での通訳を使い分けていました。公式な場では精度の高い女性のプロ通訳者(臼井久代さん)、チーム内では勢いのあるフローラン・ダバディ氏と分けることによって、公式の場では正確さを、チーム内ではスポーツならではのノリの良さを伝えようとしたようです。
ジョゼ・モウリーニョ氏
当代最高の監督として名高いレアル・マドリードのジョゼ・モウリーニョ氏は、若いころFCバルセロナでイングランド人のボビー・ロブソン氏、オランダ人のルイス・ファンハール氏などの通訳をしていました。
通訳は、言葉を上手に使えないとできない仕事です。すぐれた戦術は、過不足なく伝わって初めて優れたものになります。モウリーニョ監督の快進撃は、言語能力によるコミュニケーション能力の高さのためもあるようです。
デットマール・クラマー監督の通訳
クラマー監督の通訳を務めた岡野俊一郎さんは、厳しいクラマー監督の言葉をわざととぼけて伝えなかったり、オブラートにくるんで伝えたりすることが多かったようです。
クラマー監督の話をそのまま伝えることにより、選手が落ち込む、怒るなどの結果が出ると判断した場合に限ってですが、その尽力のかいあって、クラマー監督の功績は素晴らしいものでした。
イビチャ・オシム監督の通訳
オシム監督の通訳は、千田(ちだ) 善さんがつとめました。サッカー歴40年、シニアリーグの現役プレーヤーでもある千田さんは、オシム監督の難解な言い回しや高度なサッカー戦術論を十全に伝えられる、名通訳でした。
「リスクを冒さないサッカーは、塩とコショウの入っていないスープのようなものだ」「監督にとっては、毎回のトレーニングが選手にとっての試合に相当する」「特別なことは話していない。これまでのステップを積み重ねればよい。ただし、最後の一歩は歩幅が広い」
このような名言は、千田さんの訳があったから生まれたものです。
擬似通訳を体験してみよう
ジュニア選手のみなさまにおすすめです。
ラジオでも、テレビでもなんでもよいのですが、話している人の言葉をそっくりそのまま追いかけて言ってみましょう。ディクテーションと言い、外国語学習で良く行われている方法です。
文章を最後まで聞いてから言い始めると、次の文章に追いつきません。文章の途中から追いかけて繰り返してください。
通訳といわれる人たちは、これを外国語で行う人たちです。耳で聞くことと口から出すことがずれるとこんなに大変なのだということがわかるでしょう。これが難なくできる人は、通訳に向いているかもしれません。
「そこにサッカーがあるというだけで」
『サッカーの憂鬱』で監督の家のインターネットトラブルを解消した通訳は、テレビ電話から伝わってくる故国に残した家族を見て、ふと胸をうたれます。
外国人監督が家族を置いてきているということ。言葉もわからず、風習もわからない日本に一人で来ている理由に思い当たった通訳は、そっと心でつぶやきます。
「この国にサッカーがあるというだけで…」
サッカーがある。
それだけの理由で、故国に愛する家族を置いて単身来る外国人監督がいます。
それだけの理由で、家族を連れて言葉も何もわからない日本にやってくる選手がいます。
その人たちの心の安定や、日本での暮らしを支えているのが「通訳」なのです。
通訳になりたいジュニア選手のために
いうまでもなく、外国語は必須ですが、スポーツの通訳になるのは少し特殊です。上にも書いたように、通訳はパーソナルアシスタントのような役割も果たします。そのため、語学力はもちろんですが、監督と通訳の相性も大きな要因になってきます。
一般的に通訳になるには、大学の外国語学部を卒業したり海外の大学に留学したりして外国語を勉強したのち、通訳士の試験に合格して派遣会社や通訳会社などに登録する方法があります。
サッカーの通訳者になるには、企業通訳やフリーでの通訳活動をした後にスポーツ団体などに就職するのが一番近道のようです。留学中に知り合った人の紹介でスポーツ通訳者になった人もいますので、人とのつながりも大切になってきます。
サッカー通訳になりたいなら、
・外国語(英語だけではなく、通訳をしたい監督や選手の母国語に堪能でないといけません)
・サッカーについての知識
・監督や選手の母国の歴史や文化、行動様式
などに深い理解が必要です。
参考文献
『オシムの言葉』(木村元彦 著 集英社インターナショナル 2005年12月)
『オシムの伝言』(千田 善 著 みすず書房 2009年12月)
『通訳の技術』(小松達也 著 研究者 2005年9月)
『同時通訳が頭の中で一瞬でやっている英訳術リプロセシング』(田村智子 著 三修社 2010年3月)
最後に
テレビで監督のインタビューやニュースを見ていると、日本語音声がかぶったり字幕が出たりしますので、私たちは何不自由なく監督の言葉を読んだり聞いたりすると思っていました。
が、字幕は訳している人がいるはずですし、日本語音声も通訳している人がいます。その人たちの口を通した言葉だというのはあまり意識したことがないことに気づかされました。
言葉を伝える難しさを考えながら代表監督の会見などを見ると、違った世界が見えてくるかもしれません。