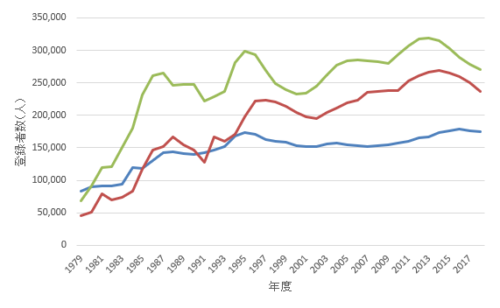2012年度全日本高等学校女子サッカー選手権大会で3位、2014年度インターハイで準優勝と全国トップレベルの実績を誇りながらも「サッカーの楽しさ」「部活の楽しさ」をベースとした指導をされている京都精華学園高校女子サッカー部の越智健一郎監督。
「チームビルディングで無人島へいく。卒部式でファッションショー。夏休みには3つのイベントを開催。全国大会直前に部員全員でディズニーランドに行く」(越智健一郎監督著書:サッカーを楽しむ心を育てて勝つ 京都精華学園高校のマネジメント術![]() より)など、ユニークな取り組みを交えながら実践している「選手との良い距離感の作り方」や「チームマネジメントの極意」についてお話を伺いました。
より)など、ユニークな取り組みを交えながら実践している「選手との良い距離感の作り方」や「チームマネジメントの極意」についてお話を伺いました。
(電話取材,執筆 江原まり)
↓本文は写真の下に続きます↓
京都精華学園高校女子サッカー部
越智健一郎監督
2006年から京都精華学園高校女子サッカー部の監督として指導にあたる。
2012年度全国高校選手権で3位、2014年度インターハイでは準優勝に輝いた。
「いつまでもサッカーを好きでいさせるためのアプローチ」(著作より)
に心を砕き、独自のマネジメント術でチームをまとめる指導法をまとめた著書を2020年上梓。
いまどきの女子高校生選手たちとの距離感とチームマネジメント
—越智先生は京都精華女子サッカー部での指導は2006年からですが、サッカーの指導歴というと24年目になるそうですね、指導を始めたころと比べて子ども達の様子は変わってきましたか?
越智先生
スポーツが習い事化してきていると感じています。
主体的、能動的ではなく、受動的、というのかな。
教えてもらう、という傾向になってきているような気がします。
昔はサッカーが好きでその辺でやっていたところの延長のような感じでやっている子が多かったのですが、今は、「何かを教えてもらう」という意識が強いですね。
これは、スポーツが整備されてきた証拠でもあるのですが。
あと、人間関係をスポーツの中に持ち込みすぎる傾向を感じています。
例えば監督と選手の上下関係、先輩後輩の上下関係など、サッカーに必要ではあるけれど、ありすぎるとよくないなと感じています。
ですから、京都精華では学年の壁を取っ払うための工夫もしています。
京都精華ではレギュラーじゃない子も楽しんでサッカーをやって欲しい。
全員が平等というわけにはいかないけれど、うまい子がサッカーを離れた場でも主導権をずっと握っているというのは不自然だと思いますし。
—先生の著書「サッカーを楽しむ心を育てて勝つ京都精華学園高校のマネジメント術」の中にはたくさんのユニークな取り組みや、独自の選手へのアプローチ方法が紹介されていますね。
越智先生
はい、学年やAチームBチーム関係なく、全員の一体感がチームの力になると思っていまして、
そのためにさまざまな工夫や仕掛けをしているという感じです。
みんなが良い雰囲気でサッカーをするには、ABCのチームわけをすることはあっても、気持ちの上での溝は作りたくないですね。
—そういった全体の一体感、ABチーム選手の溝の無さは、どういう時に活きてくるのですか?
越智先生
例えば大会を勝ち抜くには、オンオフの切り替えが必要です。
精神的に追い込んで集中しないといけない時、リラックスしないといけない時のオンオフの切り替えが必要になります。
それがAチームだけで動いていると「サッカーサッカー」になりすぎるんです。
全国大会で、Aチームが2,3日前から先に出発して、前日か当日に応援団が後から到着、そういうことは京都精華では基本的にしないです。
選手全員がみんなで同じ日に現地入りをします。
勝っても負けてもみんな一緒、という方が良いなと思って。
AチームBチームとサッカーでは分かれていても、仲が良い子はピッチ外では一緒に過ごしますよね。
そういう環境の方が自ずとリラックスできますし、オンオフの切り替えがしやすくなる気がします。
そして、何よりもチームが勝てばベンチ外の子も一緒に喜んで、負ければ一緒に悔しがる、そういう雰囲気が一番良いと思っていて。
オンとオフの切り替えができるというのは重要です。
オンとオフの切り替えが上手い人の方が社会でも成功しやすいと思うのです。
サッカーを通してオンとオフの切り替えの仕方を学ぶ。
例え大会で勝てなかったとしても、その切り替えの仕方は経験として残っていきますから。
実際、オンオフの切り替えが上手で、時間の使い方がめちゃくちゃ上手い子は、成績も良いです。
BCチームの子の方が時間の使い方が下手だったり、終わった後もダラダラしてしまったりする一面がある。
サッカーと勉強の両立ができる子は一人でも、さっさと帰ります。
女子は友達と一緒に帰る子が多い中で、です。
サッカーはサッカーという切り替えが出来ているのだと思います。
—今時の子ども達に合わせた指導をするという上では、何が大切だとお考えですか?
越智先生
昔よりも世の中が便利になってきているので、今の子たちはある意味僕らよりも進んでいると捉えることも出来ます。
自分がやっている指導がこの時代にあっているのか?という「?(はてな)」を常に持っています。
どこの会社でも顧客の年齢層が変わってくると、同じ商品を同じやり方で売っていたら売れなくなっていく。
それと一緒で、今時の子ども達にあった指導に変えていかないといけないのではないかと。
子どもたちに僕たちがついていかないと。
昔の子どもたちと違うといって、子どもたち側の変化のせいにしないということです。
彼ら彼女らが40代になった時には、今の僕よりもはるか先にいく存在になっているかもしれません。
ですから指導者が「年齢が上イコール上の立場」というようにならないようにしています。
一般企業でも顧客目線とかユーザーファーストというじゃないですか、それと一緒で、子ども目線、子どもファーストという感覚です。
いくら良い指導法を持っていても、それが伝わらなければ意味がありません。
僕の方が子どもたちに合わせていくという発想です。
指導のあり方の根源について、少し疑問を持ってみたら、新しい発想が生まれるような気がします。
—単純な上下関係ではないとすると、選手との距離感を取るのが難しいと思う方もいらっしゃると思うのですが、その辺りはどうされているのですか?
越智先生
僕と選手たちというのは、年齢の差が年々開いていきますよね。
例えば今は20才くらいの年の差だったとして、指導は常に高校生を相手にするのですから、僕と選手との年の差は年々離れていくことになります。
僕だけが上りのエスカレーターに乗っているようなものです。
それでは、どんどん離れた存在になっていってしまうので、僕は上りのエスカレーターを(逆に)下らないといけないと思うのです。
頑張って上りのエスカレーターを(逆走して)下れば、なんとかその場にとどまれますよね(笑)
これが、僕がしている「選手との良い距離感を保つための努力」です。
「選手との距離感が近くて良いよね」と周りの方に言われることもありますが、実は努力をしているのです(笑)
それでチームが強くなるなら、安いものです。
—なるほど、自分だけが上がりのエスカレーターに乗っているとは分かりやすいイメージです。
選手との距離感を近づけようと思っても、どうして良いかわからないという方もいらっしゃるかもしれません。
越智先生の具体的なやり方を教えてください。
越智先生
そうですね、人として、表情は気をつけていますよ。
しかめっ面かニコニコしている先生か、どちらが親しみやすいかといったらニコニコしている先生ですよね。
子どもたちに怖いなと思わせたくない。
今時の子が気になっている話題があれば、話のネタになるので、映画は何をやってるのかとチェックしていますし、「あれ観に行った?」みたいな話題をよく生徒に話しかけます。
それが僕の距離感の取り方の一つの方法です。
例えば「NiziU(※編集部注:ニジュー。日韓合同オーディションプロジェクト「Nizi Project」(通称・虹プロ)から誕生したガールズグループ。女子高生に人気)」の話題を知っているだけで、彼女たちと話が合う。
だいたいアイドルや映画の話は物理的に1-2メートルの距離感で話す話題じゃないですか。
その話題で話そうと思ったら、物理的に近くに寄る必要がありますよね。
サッカーだけでは、ピッチの外と中を考えたら分かりやすいですが、物理的な距離が離れていて「おーい!」と大声で声をかける感じになります。
これでは距離感が縮まらないと思います。
距離感というのは、コミュニケーションの取り方ですよね。
普段からこうしたコミュニケーションの取り方をしていると、たまに、「それちょっと違うじゃん」という話をしても受け入れてもらえる。
でも、もしたまにしか話したことの無い上司に「違うだろ」と言われたら?
「わかりました」と言いながらも、どこか釈然としない気持ちになったりしませんか(笑)
普段コミュニケーションが取れてる人から言われるのと、感じ方は違うと思います。
受け取る側は何を言われるかではなくて、誰に言われるかだと思うのです。
サッカーで勝つためには、彼女たちに僕が言ったことを受け入れてもらう必要があります。
ですから、言葉を選手たちにどう渡すか、どう行き渡らせるか、ということを常に考えています。
コロナの時でも1日2回、ラインのグループテレビ通話をして、みんなで雑談する時間を取っていました。
自粛期間中の練習内容の伝達だけではなく、雑談も織り交ぜながら7:30と13:30にグリープ通話を開始します。
1日2回というのは、質より量だと思ったので。
これも、離れていてもチームの一体感を失わないコミュニケーションの場を作る仕掛けです。
毎回45人中30人くらいが参加していました。
強制ではないので、朝だけ参加、昼は参加しないという子がいたりもありました。
参加しなかったとしても、そこは怒ったり、強制するのも違うなと思っていて。
僕は朝だけ参加して、昼は参加しませんでした。
選手たちだけの方が話が弾むこともあるかもしれないなと思って(笑)
これのおかげで会った時には、久しぶりでありながらも、久しぶりでは無い感じがしましたね。
自粛期間中のこの取り組みは、生活習慣をただすという意味でも良かったですね。
—最後に、この本をどんな人に読んでもらいたいですか?
越智先生
一般社会のコミュニケーションやマネジメントに通じるお話だと思うので、お仕事をされているビジネスマンの方や学校の先生、これから教員になろうとする人や、コーチになろうとしている方などに読んでもらえたら嬉しいですね。
自分の仕事に置き換えて読んでいただけたらと思います。
良いコミュニケーションを取るために、こういうことをしてみたらいいよ、という提案です。
こんな風に力を抜いた感じのアプローチの仕方もあるよ、ということを知っていただける機会になれば嬉しいです。
他の先生方が全国大会を目指すチーム作りをして残してきた方法もあると思いますし、私のような方法もある。
色々な方法を知っている方が良いと思いますので、「こんなやり方もあるのか」ということで読んでいただけたらと思います。
—越智先生、本日はお忙しい中、貴重なお話をありがとうございました!
関連記事
『団結・全力・感謝』が人間的成長を促す!~未来を切り開くカギがそこにある~【関西学院大学体育会サッカー部女子チーム インタビュー】
スポンサー募り部費無料化を目指す「選手を取り巻く環境を向上させたい」京都橘高校サッカー部の新たなる挑戦【米澤一成監督インタビュー】
難関大学進学と好きなサッカーの両輪で未来を掴め!~サッカーを通して人間性を高める~【函館ラ・サール高校サッカー部 葛西監督インタビュー】
常勝軍団!青森山田高校サッカー部 黒田剛監督インタビュー「日本一の育成システム」で目指すもの、コロナ禍を乗り越えるために大人たちがすべきこととは。