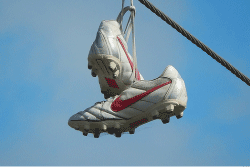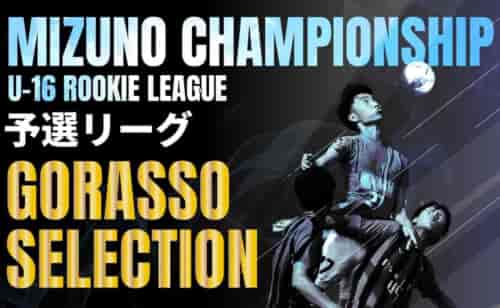将来、子どもたちの職業の選択肢になるかもしれないサッカー選手以外の裏方の職業についての第17弾です。
実業之日本社から出ている『サッカーの憂鬱 2』(能田達規著)をテキストに、サッカーの裏方の職業をシリーズでお届けします。
今回は通称フィジコ、フィジカルコーチについてです。年々重要性が認められつつあるフィジカルコーチについて少し深く掘り下げてみましょう。
「子どもたちに知って欲しい!」シリーズのバックナンバーまとめはこちら!
photo:Mark Maybell
CASE.17 あらすじ
 photo:Jon Candy
photo:Jon Candy
場面は試合中。ピッチの中で選手が一人倒れています。「根性なしめ!」と叫ぶ監督にくってかかるフィジカルコーチ。
静止されながらフィジカルコーチは心の中でつぶやきます。「強制出場すればこうなることはわかっていたのに…すまん」
フィジカルコーチとは、いったいどんな職業なのでしょう?
フィジカルコーチってどんな職業?
 photo:dasthought2002@yahoo.com
photo:dasthought2002@yahoo.com
フィジカルコーチとは、異なるコンディションの選手たちが全員試合時にコンディションのピークとなるようにコントロールするコーチのことです。
選手個人でも毎日コンディションは違います。最終的にチーム全員を同じコンディションに持っていき、きちんと90分ベストなパフォーマンスで試合に臨めるようにするコーチがフィジカルコーチです。
日本でのフィジカルコーチの普及は?
残念ながら、日本ではフィジカルコーチの普及は十分とは言えません。主にボールを持たないトレーニングをするのがフィジカルコーチですが、コーチや監督がこの役割をしているチームもたくさんあります。
J1のクラブチームの中でも、明確に「フィジカルコーチ」というスタッフを置いていないところはまだあります。
ヨーロッパでのフィジカルコーチの普及は?
ヨーロッパのトップチームにはフィジカルコーチがいるのが当然です。ヨーロッパには資格もあり、監督が異動の際に信頼できるフィジカルコーチと一緒にチームを代わることも珍しくありません。
プロ職業として深い知識と経験が必要とされ、査定基準も厳しいものがあります。その査定基準の大きなものが、
「途中出場の選手がいかに短時間で100%の力を出せるか」という項目です。
途中交代選手の活躍はフィジカルコーチ次第?
 photo:woodleywonderworks
photo:woodleywonderworks
2009年のデータですが、J1チームの途中出場選手の得点率を調べたものがあります。(試合数は、途中出場の選手が得点した試合の数です)
7試合:ガンバ大阪、柏レイソル
5試合:大宮アルディージャ
3試合:川崎フロンターレ、浦和レッズ、川崎フロンターレ、横浜F.マリノス
2試合:サンフレッチェ広島、ジュビロ磐田、ジェフユナイテッド千葉
1試合:アルビレックス新潟、大分トリニータ
2009年時点、FC東京、川崎、横浜FM、磐田、ジェフ千葉、新潟には日本人のフィジカルコーチしかおらず、大阪、柏、大宮、鹿島、名古屋は外国人フィジカルコーチがいました。
もちろん、この2009年は今からもう10年近く前。その当時はまだ日本人フィジカルコーチの黎明期だったにすぎません。現在は川崎の里内猛コーチを筆頭に優秀な日本人フィジカルコーチも次々に台頭してきています。
試合に出ている選手と、しばらく前までベンチに座っていた選手では、体の動き方が違ってきます。固まりかけている体を温め、試合の流れにすぐに乗せなくてはいけません。
適切なウォーミングアップを行い、途中出場の選手がすぐに体が動いて活躍できる状態に持っていくことも、フィジカルコーチの大事な仕事です。
選手を「出す、出さない」
 photo:Jakob Montrasio
photo:Jakob Montrasio
チームに主力の選手がいます。攻守に優れ、得点力もあります。
今週末から昇格をかけた2連戦があります。監督の首もかかっています。
主力選手は足が使い物にならなくなるかもしれない爆弾を抱えている状態です。70%の確率でその足は故障する、とトレーナーはフィジカルコーチに告げました。
選手は「絶対に出たい!結果は出す、試合に出してくれ!」と言います。
あなたがフィジカルコーチなら、この選手は出しますか?
監督なら、この選手は出しますか?
最終的に判断するのは、もちろん監督です。が、監督の判断がよりよいものになるよう助言するのはフィジカルコーチの役目です。
フィジカルコーチは、故障するとわかっている選手をピッチに送り出すようなことはしません。今期の昇格をたとえ逃したとしても、選手生命には代えられません。
「きちんと90分ベストなパフォーマンスができる状態で選手をピッチに送り出す」のがフィジカルコーチの仕事です。
ところが、監督の立場になってみるとどうでしょう。主力選手は、喉から手が出るほど欲しいはずです。
70%の可能性で故障ということは、30%の可能性で大丈夫ということ。監督はまだ選手寄りに考えてくれるかもしれませんが、フロントは?マスコミは?サポーターは?…そして、選手は?
フィジカルコーチは、このように人によって違う利害関係の中に放り込まれ、調整しなければいけない役割も持っています。
フィジカルコーチが辞めてしまう理由の一つには、「板挟みのつらさ」もあるとか。強いメンタルと高い交渉能力が必要とされます。
日本代表にはAチーム以外フィジコがいない!
 photo:woodleywonderworks
photo:woodleywonderworks
2016年3月現在の日本代表年代別Aチームのフィジカルコーチはフランス出身のシリル・モワンヌさんです。フットサル日本代表のフィジコは村岡誠さん、なでしこのフィジカルコーチは広瀬 統一さんです。
ところが、年代別A代表以外のU22,U18,U15にはフィジカルコーチはいません。コンディショニングコーチはいます。
2009年の日本代表はフィジカルコーチが不在でした。そのためか、公式戦7試合で途中出場の選手が誰も得点できなかったという事実があります。「日本代表ウォーミングアップ不足説」が流れた原因も、一つはここにあるようです。
※情報は2015年度のものです。状況が変わりましたらお伝えいたします。
フィジカルコーチとトレーナーの違い
 photo:Deane Rimerman
photo:Deane Rimerman
フィジカルコーチがいないチームにも、トレーナーはいます。トレーナーとフィジカルコーチは何が違うのでしょう?
トレーナー
接触プレーがあって選手が倒れた時、ベンチから荷物を持って駆け出すジャージ姿の人がいます。この方がトレーナーです。応急処置、担架の要請などを行います。
選手のケアを行いますが、主にメディカルケアを行います。そのため、鍼灸やマッサージ、カイロプラクティックの資格を持っている方が多いです。
ドクターの補助的な役割を担うだけではなく、運動能力を高めるためのトレーニング指導も行います。チームにフィジカルコーチがいるところでは、フィジカルコーチの補佐を行います。
スポーツジム、整体院から派遣されるケースも多いようです。
フィジカルコーチ
現代のサッカーにおけるフィジカルに関する考え方は、「サッカーに必要な肉体はサッカーをやることで鍛える」という考え方が主流です。
ボールを使ったメニューそのものにフィジカル向上のための要素を取り込んでいかねばなりません。
より専門的に、「身体」に対する知識を持ちつつ、フィジカルを効果的に向上させ、選手の持っている能力を100%引き出すことのできるのがフィジカルコーチです。
フィジカルコーチを目指すジュニア選手のために
 photo:popofatticus
photo:popofatticus
フィジカルコーチの資格は、まだ日本にはありません。ヨーロッパには資格制度がありますが、日本でははっきりとしたフィジカルコーチ育成の場はまだまだ少ないのが事実です。
スポーツ専門学校など、トレーナー専攻科の中にフィジカルコーチコースがあるところがあります。即戦力としてのスキルが必要とされる難しい職業である上に、まだ就職の道は開かれていないのが現状です。
フィジカルコーチになりたい場合は、サッカーを続けながら幅広く勉強し、日本体育協会の認定資格であるアスレチックトレーナーの資格を取っておくとよいでしょう(アスレチックトレーナーは民間資格です)。
現在活躍しているスポーツトレーナーの中には、アスレチックトレーナーの資格を持っていない方もたくさんいます。今後、必要とされてくる資格のようです。
最後に
途中出場の選手がピッチに入るときは緊張やリズムのずれを早めに修正する必要があります。だからピッチに入ってきた選手にはなるべく早くボールを持たせるようにするのだと、いつかインタビューで聞いた覚えがあります。
ピッチの中にいる選手たちの気遣いもそうですが、ピッチに送り出す前のフィジカルコーチの手腕が、このファーストタッチを活かすか殺すか決めるのかもしれない…と思いました。
おまけ
 photo:Anthony Easton
photo:Anthony Easton
フィジカルコーチとは関係ないですが、フィジカルコーチの情報を集めていく中で見つけたおまけのコーナーです。
■大分トリニータの「選手へのファンレター募集」コーナーには郵送先が書いてある
(選手への応援のメールフォームが載っているチームはたくさんありますが、郵送先が載っているのはとても珍しいです!)
■子どものころから人工芝でプレーしていると、人工芝が原因のケガはほとんどないらしい
(うらやましい環境ですが、天然芝から人工芝へ急に移るとケガをしやすくなるようです)
■最初のフィジカルコーチは陸上のフィジカルコーチだった
(試合のスパンの違いからだんだんとサッカー専門の人が求められるようになっていった模様です)