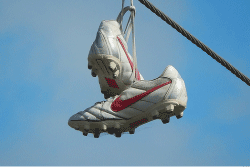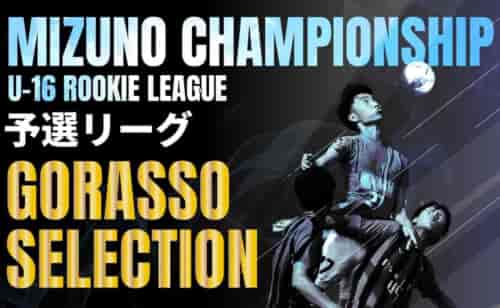将来、子どもたちの職業の選択肢になるかもしれないサッカー選手以外の裏方の職業についての第11弾です。
実業之日本社から出ている『サッカーの憂鬱』(能田達規著)をテキストに、サッカーの裏方の職業をシリーズでお届けします。
今回はターフキーパーについてです。ターフキーパーという職業について、少し深く掘り下げてみましょう。
「子どもたちに知って欲しい!」シリーズのバックナンバーまとめはこちら!
photo:Soft Surfaces Ltd
CASE.11
場面はスタジアム。「浜松バンディット こどもスタジアム探検隊」が始まります。
次はいよいよスタジアムに入ります。プロの選手がプレイする芝の上に乗るために、子どもたちがまず靴を消毒します。はしゃぐ子どもたちにターフキーパーが一言。
「あんまり無茶しないでくれよ。俺の芝が痛んじまう」
芝をほめてもにこりともしないこのおじさんがターフキーパーです。
※浜松バンディットは、『サッカーの憂鬱』の中に設定されている国内1部リーグのチームの名前です。
ターフキーパーとは?
ターフキーパーとは、グラウンドの芝を管理する職業の人です。グラウンドキーパーの呼び名のほうが一般的かもしれません。芝管理人とも言います。
一般的なスタジアムのグラウンド(ピッチ)は、シーズン中はJリーグの試合、その合間を縫ってユース年代の大きな試合などに使われています。シーズンオフにはジュニアユース、ジュニアの試合やイベントに使われることもあります。国際試合が入ってくることもあります。
ターフキーパーの仕事は一年を通じて行われます。季節によって、天候によって左右されることなく、いつも高品質の芝を一定の状態で供給しなければならない縁の下の力持ちです。
ターフキーパーがいないと、どうなる?
グラウンドにはプレイイングクオリティというものが求められています。
芝の品質検査をするような調査なのですが、次のようなことを調査します。
プレイイングクオリティの内容
・一定の高さから落としたボールがどこまで弾むか(ボールの弾みテスト)
・定められた角度からボールを滑らせ、どのくらい進むか(ボールの転がりテスト)
・地表面の硬度
このような項目は数十に及びます。しかも、グラウンドはプレイ中に芝にかかるストレスが場所によって異なるため、5か所で測定されます。これらの調査の結果が一定以上の品質にならないと、サッカーの試合を行うことが難しくなります。
ターフキーパーがいないと、芝が伸びすぎ、地表は荒れ、地面が固くなります。つまり、ボールの弾みにムラができ、バウンドする方向も一定になりません。芝が伸びることによって摩擦力が働くようになりますからドリブルやパスのボールスピードも落ちます。
40代以上の保護者の方は、Jリーグ発足前後の荒れたピッチを覚えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。ゴール前には水たまり、ところどころはげた芝、変なところでバウンドしてしまうボール…キックで力を込めた時に滑ってしまう選手もいました。
現在のJリーグのスタジアムの芝は、あのころに比べると雲泥の差です。それは、ターフキーパーのようなプロ職人がプレイイングクオリティをしっかり実現している努力のたまものなのです。
ターフキーパーの日常
ターフキーパーの仕事を通常業務と試合前、試合後に分けてみました。
通常業務
・伸びた芝を刈る
・水やり
・病気や虫のチェック(虫がついていたり病気になっていたら薬をまく)
・砂まき(水はけを保つため)
・雑草を抜く
・肥料をまく などの手入れ
試合の日の業務
・ストライプが出るようきれいに芝を刈り、白いラインを引く
・試合は双眼鏡でチェック(キックなどの時、剥がれた部分を確認するため)
・ハーフタイムには、ちぎれた芝を拾い、砂と芝の種を混ぜたものを芝が剥がれたところにまいて凸凹を直す(放っておくと損傷が大きくなる)
ストライプの幅は、5m50㎝に定められています。オフサイドを分かりやすくするためです。日本代表の試合などを見ると、ペナルティエリアはストライプ3本分になっています。ストライプは見た目だけでなく、副審にとっても目安になるのです。
ちなみに、ライン引きも仕事のうちです。ラインは12cmの幅に引きます。
試合翌日の業務
・ピッチの修復
大きな穴には別の場所で育てていた芝を植えたりもするようです。きれいな芝生に戻し、次の試合の準備をします。
他に、ターフキーパーの仕事としては、ゴール立て、ネット張り、コーナーフラッグ建て、練習場などの人口芝の清掃なども含まれます。
家庭の芝とどう違う?
芝の種類
2005年にベストピッチ賞に輝いた埼玉スタジアム2002には、次のような芝の種類が混生されています。
◆ケンタッキーブルーグラス(霜の時期まで緑色を保つ)
◆トールフェスク(踏まれても弱りにくい)
◆ペレニアルライグラス(発芽と成長が非常に速い。熱さと湿気には弱い)
これらも含め、3系統6種類の種をまいているようです。
土地の地質
発芽しやすく、成長を促し、何より地面が固まりすぎないように、洗った砂を25㎝の厚みに敷いています。砂は、鬼怒川産の4m/m ~ 0m/mの粒度のものを使用しています。
砂を使うのは、スタジアムの水はけを促すためでもあります。雨でも行われるのがサッカーの試合ですが、降っている雨のわりにピッチに水たまりができないのは、土地作りに理由があります。
水
中水を使用します。撒く面積が広いので、たくさんの水を必要とします。中水とは、上水と下水の間の水になります。飲むことはできませんが、下水に流すのはもったいない雨水、雪解け水などがこれに当たります。
コアリング作業
パイプ状の棒を地面に差し、芝草を抜き取る作業です。芝の根に空気が入って生育が良くなる効果があります。土が固くなりすぎるのも防ぐ効果があります。
スパイキング作業
丸い棒を地面に差し、空気を入れます。コアリング作業と狙いは一緒です。
サッチング作業
枯れた葉や、茂りすぎた部分を取り除く作業です。芝の風通しを良くします。
風通しを主目的として行われる以上3つの作業を、まとめて「エアレーション作業」「更新作業」とも呼びます。
埼玉スタジアムでは、9人のグラウンドキーパー(埼玉スタジアムの芝管理人は、グラウンドキーパーと呼ばれます)が365日、ローテーションで芝を管理しています。
台風が来た!
グラウンドキーパーの一番の敵は、台風かもしれません。短時間に大量に降り注ぐ雨は、水はけのよいグラウンドでも水たまりを作る可能性があります。
サッカーの試合は原則として雨でも行われます。台風などの公共交通機関が止まった場合、雪や雨によりピッチにボールが転がらない部分ができてしまった場合にも中止になることがあります。噴火による火山灰の降灰、砂嵐のときも中止になった例があります。
つまり、試合前日の台風で、当日水たまりがたくさんできてしまっていた場合は、「ボールが転がらないところ」があるとして試合が中止になる可能性があるのです。
台風が来ると、夜中にもかかわらず芝の様子を見に行くターフキーパーもいます。台風などの嵐の際、外に出ることはそれだけで危険を伴います。
水たまりひとつなく、芝が青々としているグラウンドは、ターフキーパーの誇りなのです。
ターフキーパーになりたいジュニア選手のために
鋭いパス、切り裂くドリブル…これらを支えているのは、選手の足元にある芝を管理するターフキーパーです。
手入れを怠ると、芝はぼうぼうに生えてしまいます。すると、ボールがバウンドした時に方向がずれたり、ドリブルの速度が落ちたりということにもつながる可能性があります。
選手たちの華麗なプレイを支えるターフキーパーになるには、次のような道があります。
ターフキーパーになるには
一般的には、高校や大学を卒業した後、造園会社や競技場管理会社に入社します。特別な学歴は必要ありません。
各大学の農学部には、芝に関する研究を専門的に行う教授もいます。どうしてもターフキーパーを目指すなら、そうした教授に教えてもらえる大学へ行くのが良いでしょう。あまり数が多くありませんので、大学を決める際には良く調べるようにしてください。
造園を専門に教える専門学校もあります。学校や大学などを調べる際には、卒業生の就職先に競技場管理会社があるかないかも目安になります。
専門的な技術を持ち、どちらかというと職人に近い側面のあるターフキーパーですが、ターフキーパーは会社に雇われているサラリーマンのため、収入は平均的だということです。
最後に
小学校の校庭も芝生にするところが増えてきました。近隣小学校がちょうど去年芝生になったのですが、週に2,3日は管理人の方が来て手入れをしているようです。
どんな方が管理しているのか聞いてみたところ、もともとゴルフ場の芝の管理をされていた方が、定年後近所のよしみで手伝ってくださっているということでした。
こまめな世話をしないと、芝はあっという間に茂ります。もともと生育が早い植物ですし、意外に固いので、放っておくと小学生の足には痛いほどになってしまうのだとか。
きれいなピッチも、途方もない努力のたまものです。サッカー観戦に行ったときは、ぜひハーフタイム中のターフキーパーさんの動きも見てみてください。