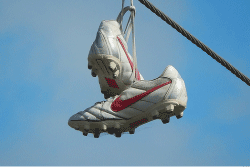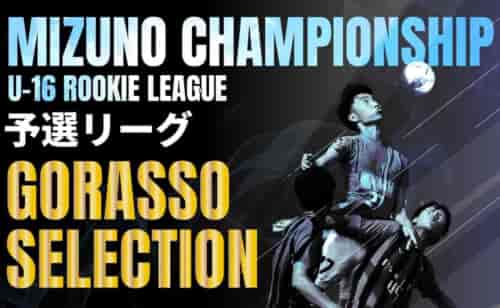プロスポーツ選手の自叙伝などを読むと、「親にはマッサージをしてもらっていた」という記述に出会うことがあります。代表的なのは、野球のイチロー選手でしょうか。よりよい体調とプレーのために、親がしてあげられることはないか?を調べてみました。
photo:Irina Patrascu
親のマッサージにある2種類の効果
 photo:Markus Tacker
photo:Markus Tacker
してあげられること、といって最初に思いつくのはマッサージだと思います。親のマッサージはお子さんには特に大きな効果があります。おもな効果をまとめました。
「体をほぐす」効果
スポーツをしている子は、体に疲労をためます。どんなに回復が早い子でも、疲労がたまっていることに変わりはありません。疲労とは、乳酸をはじめとした疲労物質がたまってしまう状態のことを言います。
親が少し手を添えてその部分をさすってあげることで疲労物質を流し、翌日の練習に向けて体が回復モードに入ることができます。
「心をほぐす」効果
マッサージは、スキンシップです。体をほぐすマッサージは、最大限の効果を生み出すには熟練が必要で、そのためにプロのマッサージャーがいます。
保護者が子供に行うことができるのは、医療行為ではなく癒し行為です。マッサージをして気持ちが良くなると、子どもの口がほぐれてきます。今日の反省や嬉しかったことなどを話し合う時間になっている人も多いようです。
マッサージの際の注意点
 photo:mararie
photo:mararie
運動をしている子どもの筋組織は傷みやすいものです。ほぐす目的のマッサージですから、絶対に痛くならないようにしましょう。
痛くなると、その部分の神経には緊張が生まれ、その部分の筋肉がこわばります。今日酷使した筋肉は、休息しないと「超回復」という、さらに強くなる筋肉へと変化していく働きができなくなります。
整体などで体のゆがみを直す際の痛いマッサージは、ドクターにゆだねましょう。親が子供にしてあげるマッサージは、ちょっと気持ちいいくらいで十分効果があります。
親が子にしてあげるマッサージの方法
 photo:Michael Johnson
photo:Michael Johnson
サッカーで酷使する部分は、
・股関節
・足
・腰
・足首
・足裏
です。
そのうち、マッサージに向いているのは
・腰
・足
・足首
・足裏
です。股関節は、他人には痛みや状態が分かりにくいもの。こちらはストレッチを教えて自己管理させた方がよい場所です。
腰のマッサージ
腰骨の少し上を、体重を少しかけてゆするようにさすります。かける体重は、お子さんの年齢や体格によって加減してください。ちょっと気持ちいいくらいが一番いいのです。
腰の筋肉が固まると、腰痛の原因になります。筋肉をほぐすように揺らしてください。力のかけすぎは禁物です。
足のマッサージ
ふくらはぎを、下から上へ、下にたまっている乳酸を上半身へ押し上げるようなイメージでさすり上げます。左右20回ほど、あまり強く押しすぎないようにしてください。ふくらはぎのマッサージは、同時でなくてもかまいませんので、かならず両足行います。
ふくらはぎは、「下半身の心臓」と言います。ここをマッサージして押し上げてあげることで、ポンプ機能を正常に保ち、足の早い疲労回復が見込めます。
足首のマッサージ
アキレス腱のケアをします。が、アキレス腱そのものを押してはいけません。うつぶせに寝た状態で、アキレス腱の脇に両手の親指を添え、ゆっくり伸ばしてあげましょう。
痛がるのは、無理な力がかかっている証拠です。様子を見つつ、弱い力から始めましょう。
足裏のマッサージ
足の裏の中央を、足先に近いほうからかかとに近いほうまで順々に押していきます。痛がる部分があったら、優しく押して様子を見ましょう。優しく押したときに痛みが消えて、気持ちが良くなるようなら弱めに押して様子を見ます。
優しく押したのに、痛がるようならその部分は故障している可能性が高いので、触らないようにして様子を見ましょう。何日かおいても痛がっているようなら、足底筋膜炎などの故障が起きている可能性があります。
足裏には、土踏まずと言われるアーチがあります。ジャンプなどを伴う運動をしすぎてしまうと、アーチがつぶれてしまうのです。アーチがつぶれると、足に無理な力がかかるようになっていき、脚の形が崩れてしまったり、慢性的に痛みを抱えるなどの故障に繋がります。
アーチ保全の意味でも、しっかりマッサージしてあげてください。痛がったら、すぐに力を弱めてくださいね。
足の疲労回復に効くツボ
 photo:Mr Hicks46
photo:Mr Hicks46
ツボ治療というのは不思議なもので、自分で押すよりも他人に押してもらったほうが絶対に気持ちがいいようです。
足の疲労回復に効果のあるツボは、2つあります。
三陰交(さんいんこう)
足首の内側のくるぶしから、ゆびを横にして4本分上にあります。
下半身の水のめぐりを良くするツボとして知られ、冷え性などの改善にも押されるツボです。血行を良くする効果があります。
足三里
膝のお皿の上に手の親指を乗せます。そしてまっすぐ手を伸ばしたところの中指が当たる場所が足三里です(三里は腕にもあります)。
他にも、こんなツボがあります。
ツボ百科 知っておくと便利な、体がラクになるツボ。(参照サイト:サワイ健康推進課)
アロマの話
長谷部選手の「心を整える。」でもおなじみになったアロマテラピーですが、実は嗅覚というのは脳に直結しているため、アロマにはダイレクトに脳に働きかける効果があります。
香りが脳に到達するのは、わずか0.2秒。体の痛みが脳に伝わるには0.9秒かかるそうなので、いかに早いかイメージしてください。けがをして「痛っ!」と思うより早く、アロマの刺激は脳に到達します。本当に、一瞬の出来事です。
アロマ精油の効果については、新星出版社・和田文緒著『アロマテラピーの教科書』を参考にしました。
リラックス効果のあるアロマ
 photo:Bob Cox Photography
photo:Bob Cox Photography
長谷部選手の愛用している「ナイトタイム」というニールズヤード社の製品はスティックタイプのパヒューム(コロンのようなものです)で、ジュニア年代の選手にはそうそう使えませんが、お部屋で蒸気とともにたいたりする用途で、サッカー選手に良いものを調べてみました。
ラベンダー
心を鎮め、緊張を和らげる効果があります。効果が高いので、緊急時に使うレスキューアロマとしても知られています。副交感神経を活性化させ、リラックス状態に導きます。
ローズオットー
ネガティブな感情を癒し、心を慰める香り。落ちこんだ時に使うと、ゆっくりと気持ちが引き上げられます。脳の下垂体や視床下部を刺激するので、ホルモンバランスも整える効果があります。
カモミール・ジャーマン
気持ちを大きく持つ効果があります。少量の使用で十分な効果があります。ストレス解消にも良い影響があります。
ネロリ
ストレスにより、何か体に不調が表れてしまっている時に効果があります。イライラ、攻撃的なとき、興奮してしまっている時にも効果があります。
疲労の早期排除ができるアロマ
アロマテラピーが選手の乳酸の早期排除に対して有効であることは、実験結果が示されています。
ここで扱われているジュニパー、サイプレスのオイルは次のような効果があります。
ジュニパー
気持ちをほっとさせてくれるアロマです。静脈やリンパを刺激し、腎臓機能を高めるので老廃物の排出に役立ちます。スポーツ後のアフターケアに、臨床例として実際に使われています。
サイプレス
感情の起伏が激しいとき、気持ちを落ち着けてくれる効果があります。心拍と呼吸頻度を低下させ、呼吸を深くし、副交感神経の働きを高めて血液循環を促してくれる効果があります。
スポーツアロマテラピーによるスポーツ選手の乳酸値変換(参照サイト:日本アロマ環境協会)
なかなか眠れないときに効くアロマ
精神神経系にリラックス効果を与えるオレンジ・スイートなどの香りがお勧めです。
オレンジ
スイートとビターがありますが、お子さん向けにはスイートがお勧め。精神安定の効果が強いのはビターのほうですが、スイートのほうがリラックス効果は高いです。安眠に効果があり、前向きで元気な気持ちにしてくれます。
リラックスで取り上げたラベンダーも安眠に効果があります。
研究データはこちら
No.3 オレンジ・スイート精油がもたらす就眠前不安への生理的影響(公益社団法人 日本アロマ環境協会)
アロマを使用する際の注意点
 photo:Kazuhiro Keino
photo:Kazuhiro Keino
アロマは、植物から抽出した天然成分を濃縮したもの。作用は大変強いものです。このため、次のような注意が必要になります。
肌に直接塗らない
作用の強い成分のため、肌に直接つけると皮膚炎の原因になったりします。肌に直接つけたい場合は、キャリアオイルと呼ばれる無臭のオイルにごく少量を混ぜてつけます。
天然精油がおすすめ
安価なもので、合成のアロマも売っていますが、効果を求めるのなら、天然成分100%のものを求めてください。不純物が、思わぬ逆効果になる場合もあります。
手軽にできるのは蒸気にする方法
インテリアショップなどで売っているアロマライトやアロマディフューザーなどを使うのがおすすめです。洗面器にお湯と1滴のオイルを入れて頭からバスタオルをかぶって吸入する方法もありますが、アロマライトなどを使えばその部屋にいるだけで気軽に吸入ができます。
アロマバスもおすすめ
一般的な浴槽にアロマの精油を2,3滴入れれば、気軽に蒸気吸入と皮膚からの吸入を行うことができます。
400Lの浴槽でも、上限は6滴まで。自分の好きなオイルをブレンドすることもできるので、人気の方法です。精油は高温多湿に弱いので、お風呂場に置きっぱなしにするのはくれぐれも避けてください。
ストレッチのすすめ
 photo:Tony Alter
photo:Tony Alter
保護者が子供にしてやれることは、直接的にやってあげられるマッサージやツボ押しだけではありません。自己管理の方法を教えるのも大事な「してやれること」です。
もちろん、クラブチームや部活でも、コーチや監督から自己管理の方法は習います。しかし、習うことと、習慣としてすでにやっていることでは、活用が全く違ってきます。
自己管理とは、次のようなことを言います。
・自分の体調が万全かどうか、察知する力
・万全でない場合、メンテナンスする力
それぞれについてみていきましょう。
体調察知力
自分の体は今いつも通りなのか、どこかおかしいのかを察知する力です。
熱があるなしから始まり、上級者になると、今日の股関節の可動域はいつもより狭いからストレッチを入念に行ってから練習をしよう、などという判断ができるようになっていきます。
メンテナンスする力
これは、知識と密接に関係しています。最近ねん挫が多いから、ねん挫をしないようにケアしたいなあと思っても、どうすればいいのかわからなければケアは不可能です。
メンテナンスのために、ストレッチは「目的」をはっきり理解しておきましょう。いくつか例を挙げてみます。
長座体前屈は、「腰部」と「大腿部」の筋肉を柔軟にするために行うものです。
あおむけに寝て片足の膝を抱え込むストレッチは、股関節の前部分とお尻の付け根に柔軟性を持たせるためのストレッチ。
それぞれのストレッチによって伸ばす部分が違います。難しく考えなくてよいので、どの部分が伸びているかを考えながら伸ばすようにとアドバイスしましょう。自分でもやってみると、どこが伸びているかわかります。
ストレッチに向いている時間帯
筋肉は、ゴムのようなものです。冷えた状態では可動域が狭く、温めた状態では広くなります。
昔から、「柔軟はお風呂上りに」と言われるのは、「温めたほうが筋肉や腱はのびやすい」という裏付けがあります。お風呂上がりでなくても、体が温まっていればよいので、練習後は最適です。
ストレッチの効果
筋肉が固くなるのは、選手にとって致命的です。筋肉が固くなるのには二つのタイプがあります。
○過用性委縮
偏った使い過ぎで筋肉が硬化して委縮してしまうことです。スポーツ選手の肉離れなどは、過用性委縮を原因とすることが多いようです。
○廃用性萎縮
筋肉を使わないことで筋肉が弾力性を失い、硬化してしまうことです。運動不足が原因で起こります。普段意識して運動をしていない方が急に激しい運動をすると腱や筋肉を傷めるのは、委縮している筋肉をむりやりのばそうとして筋繊維が傷つくのが原因です。
ストレッチは、どちらの筋肉の萎縮も軽減させる効果があります。ゆっくり行うことによって血流も良くなりますので、リンパや血液の循環も良くします。血液の流れが順調だと、冷え性もなくなりますし疲れも早く取れます。
筋肉は、激しく使ったあと、そのままケアを不十分にして使い続けると「過用性委縮」となります。良い筋肉を育てるには、筋肉を使った後、適度な休息と栄養を得てまたトレーニングすることが必要です。
ジュニアの体調管理の推移
 photo:amrufm
photo:amrufm
どこまで親がかかわればよいのか?どこから自立心を求めればいいのか?ということで悩んでいる保護者も少なくありません。過保護なのではないか、やりすぎなのでは、あるいは、やらなすぎなのでは…そんな方のために、ジュニアの発達段階をまとめてみました。
ジュニアの体調管理について、どこまで親がかかわるのが理想的か見てみましょう。ちなみに、これはあくまで健康面の管理です。食事面の管理はずっと続きます。
保護者が面倒を見てあげないといけない時期(4~7歳)
自分の体調について、関心がありすぎる子と無関心な子に分かれている時期です。運動神経は5歳くらいで80%が出来上がります。これらの神経の発達が終わらないと、体調に注意が行かないという説もあります。
無関心な子は、自分が高熱が出ていることにさえ気が付かない子もいるほど。関心がありすぎる子は、「2週間前の傷がまだ痛い」など、昔の傷を思い出してはその部分が痛くなったりします。
この時期のサポートは、ほとんどが大人にゆだねられます。体調が悪そうだったら熱を測ってみる、痛みがあったら適宜休ませるなどの判断は、親が下すほうが間違いがありません。
まだまだ保護者が面倒を見てあげないといけない時期(7~9歳)
神経系統の発達は落ち着いてきますが、ここで「9歳の壁」という、抽象的なものを考えられる頭への大きな変化があります。
自意識も高まってきますので、熱や痛みがあっても「大丈夫!」と言い張ることの多い時期です。
個人差はありますが、いろいろなことが理解できるようになります。痛い理由や、痛みを放っておいてはいけないことを教えてあげるには最適な時期です。
自己管理をだんだん教えなければいけない時期(9~12歳)
運動神経の発達がほぼ100%終了します。自分の体調について、ようやく自覚し、管理できるようになる時期です。
スポーツの自己管理の最たるものは、ストレッチなどの自己メンテナンスです。自分の体の調子をどうやったらいいものに持っていけるか、を教え始めるのに最適です。
自己管理を尊重しつつ、サポートしなければいけない時期(13~15歳)
第2次性徴を迎えます。体が急に変わりますので、クラムジーなどの現象も起きます。厄介なことに、思春期も始まりますので、親の言うことはあまり聞かなくなります。
理想は、この時期までに自己メンテナンスの方法を伝え終わっていること。そして、選手自身の判断を尊重しながら、親はサポートに回ることができれば、親子間の感情トラブルの少ない中学時期が乗り切れるようです。
クラムジーとは、第二次性徴期に身体と感覚のバランスが崩れることによって起きる現象です。今までできたことが急にできなくなったりすることが起きます。これを「下手になった」「つまづき」と感じ、落ち込んでしまう選手も多いのです。
自己管理に任せる時期(15歳~)
早い子では、15歳から高校やクラブユースの寮に入ってサッカーに打ち込む子も少なくありません。保護者の手をほぼ完全に離れる状態です。
家にいても、親の言うことを聞く時期は過ぎました。「聞いてもやらない」などのことが増えてくるのも特徴です。強豪校や強豪チームほど、「選手の管理は選手の仕事」として、選手の自主性に任せることが多くなっています。
最後に
今回この記事を書くために、整体院の先生にお話を伺いました。そのときに先生がたいへん強調されたのが、「やってあげるのはとても良いことだが、自分で自分の体に関心を持つことを教えるのもとても大事です」ということでした。
確かに、15歳で完全に親離れすることを考えると、面倒を見られるのはほんの数年ですよね。サッカー人生がそのあとも続くことを考えると、自己管理はできたほうが親の心配も減ります。
年代によって、子どもの成長は著しいもの。発達段階に合わせた関わり方で、子離れの日を上手に迎えたいものです。